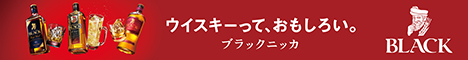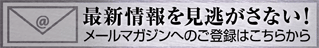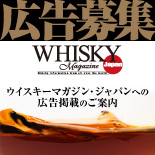富嶽蒸溜所のウイスキーづくり【後半/全2回】
 清らかな水と堅実な設備から生まれる芳醇なスピリッツ。その香味にはウイスキーを愛してやまない創業者の理念が込められている。
清らかな水と堅実な設備から生まれる芳醇なスピリッツ。その香味にはウイスキーを愛してやまない創業者の理念が込められている。文・写真:ステファン・ヴァン・エイケン
製造設備について案内してくれるのは、富嶽蒸溜所ヘッドディスティラーのピエール・フランクさんだ。フランス出身で、来日して11年になるという。
「高知県で8年間さまざまな仕事を経験した後、現地で酒造メーカーに就職しました。栗焼酎が有名ですが、冬には日本酒を造る経験もできました」
四国で働いていたフランス人が、なぜ富士山麓の真新しい蒸溜所でウイスキーをつくることになったのだろう。
「妻がネットで求人広告を見つけて、SASAKAWA WHISKYのウェブサイトにたどり着いたんです。ゼロから新しいことを始めるのはワクワクするし、創業メンバーの一員になれることにやりがいを感じました」
こうしてピエールさんは妻と幼な子を連れ、3年前に富士吉田に移り住んでプロジェクトに参加した。現在、富嶽蒸溜所でウイスキー製造に携わるのはピエールさんを含め10人。その半数は酒造業務の経験者で、残りの半数は大学を卒業したばかりの新卒者や異業種からの転職者だ。社長の笹川正平さんは、週に3日ほど蒸溜所の現場で過ごし、残りの1週間は東京で過ごす。

ピエールさんの案内で、製造棟を見学する。まずは製粉室からスタートだ。製粉機(ドイツのキュンツェル社製)と木製の発酵槽以外は、すべて三宅製作所の製造である。バッチあたりの麦芽使用量は1トン。当初はノンピートの麦芽のみを使用していたが、2024年9月に初めてヘビリーピーテッドの麦芽(50ppm)を試験的に使用してみた。
今後は、ピーテッド麦芽とノンピーテッド麦芽の使用を季節ごとに分けるという伝統的なアプローチに落ち着いていく見込みだ。ピーテッド麦芽の原酒生産量については、まだ決定していない。2024年11月末から2シフト制が導入され、1日2バッチの週7日稼働という生産体制になった。蒸溜所が生産を完全に休止する期間もないので、ほぼ年中無休稼働である。
糖化、発酵、蒸溜は、すべて同じコンパクトな部屋の中で遂行される。作業にあたるスタッフから、すべての工程が同じ目線の高さでチェックできるようにレイアウトされている。このような合理性は、設計時からはっきり意図されたものだと正平さんは説明する。
糖化は3回に分けてお湯を投入する標準的な方式で、ワンバッチから約5,400Lの麦汁を得る。麦汁は6槽あるオレゴンパイン材の木製発酵槽(全部で容量7,000L)のひとつに送られる。ステンレスではなく木製にした理由も正平さんが教えてくれた。
「乳酸発酵を促したかったので、木製のウォッシュバック(発酵槽)が欲しいと思っていました。メンテナンスは大変ですが、今のところ順調です」
酵母にはウイスキー用酵母を使用し、発酵時間は季節によって左右するが、だいたい3~4日だとピエールさんが言う。
「夏は3日で十分ですが、冬はもう1日必要ですね」
今年の夏には新しい発酵槽2槽を加え、スピリッツの生産量を倍増させる予定だ。
豊かな香味を得るための製造設備
ポットスチルは初溜器と再溜器が1基ずつあり、ともにヘッドがストレート型だ。初溜器(容量6000L)のラインアームは下向きで、再溜器(3300L)のラインアームは水平になっている。どちらも多管式(シェル&チューブ式)のコンデンサーで蒸気を液化する。

初溜器は直火式(ガスバーナー)であるのに対し、再溜器は間接加熱式(スチーム)である。この興味深い違いについて、正平さんが理由を説明する。
「この地域の湧き水は軟水なので、とてもクリーンな酒質になりやすいことがわかっていました。ニューメイクスピリッツの風味をもっと力強く複雑にするため、初溜器には直火式を採用するのがいいだろうと考えたのです」
そのニューメイクスピリッツを実際にテイスティングしたみた。非常にエレガントかつクリーンでありながら、複雑なフルーツ香やモルト香も満ちている。まだ樽熟成の恩恵を受ける前なのに、まろやかで飲みにくさを感じさせない。
ピエールさんによれば、初溜器の火力はコントロールがとても難しいという。初溜には約6時間、再溜には約5時間半ほどの時間がかかる。バッチごとに約550Lのニューメイクスピリッツがつくられ、6バッチが溜まったらニューメイクスピリッツを度数63.5%に希釈して樽に充填する。
蒸溜所の敷地内には、2つの貯蔵庫がある。第1貯蔵庫はダンネージ式で、すでに満室(約450樽)となっている。第2貯蔵庫は蒸溜所本館の裏手にあり、移動式ラックで約1,900本の樽を収容できる。訪問時には約700の樽が収納されていおり、その大部分(約90%)はバーボン樽だった。残りのほとんどはシェリー樽である。これまでに充填された樽のうち、5本はミズナラ材のホグスヘッドだ。
ピエールさんは樽の調達のために2024年11月にしばらくスペインで滞在した。その成果として、今年以降はさらに多くのシェリー樽が蒸溜所に届けられる予定だ。笹川正平さんは、グレンファークラスが好きだと公言している。それを念頭に置けば、シェリー樽熟成の重視も驚くことではないだろう。正平さんが語る。
「グレンファークラスの風味は、わたしたちのウイスキーにとってベンチマーク的な存在だと思っています」
ここ富士吉田市は、標高約900mでスコットランドによく似た気候だ。そんな熟成環境が、今後何十年にもわたって富嶽蒸溜所のハウススタイルを形成していくことになる。どんな香味に結実するのか、たびたび経過をチェックできたら面白いだろう。
ビジターセンター、ホテル、レストランなど、蒸溜所が成長する未来についても考えるべきことはたくさんある。地元のミズナラ材から樽を造ったり、ワイン王国である山梨県のワイナリーから樽を調達する可能性も探っているところだ。だが笹川正平さんは、最初の製品の発売時期について特にスケジュールは決めていないという。
「熟成が完了したと納得できたら、その時点でウイスキーを瓶詰めして発売します。正直なところ、ウイスキーづくりのビジネス的な側面についてはあまり考えていません。ただ自分の夢に従うだけ。ウイスキーが大好きで、それがウイスキーをつくろうと考えた唯一の理由ですから」