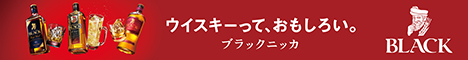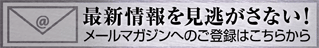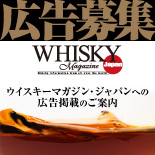ミズナラ樽の真実【後半/全2回】
 ミズナラ樽熟成を謳ったウイスキーには、専門家から疑念の声も上がっている。本当の魅力を知るために、まずは樽材としての特性を理解しよう。
ミズナラ樽熟成を謳ったウイスキーには、専門家から疑念の声も上がっている。本当の魅力を知るために、まずは樽材としての特性を理解しよう。文:マーク・ジェニングス
ミズナラ樽がウイスキーにもたらす風味プロフィールの内容については、多くのことが語られてきた。サンダルウッド、寺社の線香、ココナッツ、エキゾチックなスパイスなどといった香りは、西洋人にとってミステリアスな神話を想い起こさせる。だがそのように語られるミズナラ樽の本質は、どれほど正確に説明されているのだろうか。ウイスキー評論家のデイヴ・ブルーム氏が大きな疑義を呈する。
「まず誰もがミズナラ樽の特徴だと言いがちな『お寺のような香り』は、誰でもすぐに感じられる香味要素ではありません。あとから微かに感じられる人がいたとしても、お寺のような香りを感じるには樽が適切に造られている必要があります」
サントリーのブレンダー室やヘリオットワット大学の博士論文などが公表している科学的研究によると、ミズナラ特有の香りは、木材の奥深くにある複数の化合物がゆっくりと相互作用することで生まれてくる。そしてこのような相互作用は、数カ月程度の熟成で生まれるものでは決してないとブルーム氏が説明する。
「ラベルにミズナラの文字を書きたいがために、形だけミズナラ樽を使用しているウイスキーメーカーもあります。ウイスキーの原酒を6 か月間だけ樽に入れて『寺のような香り』を謳ったりしていますが、あれはナンセンスですね。高額な価格設定に見合った熟成とはいえません」
有明産業の営業部長を務める坂本賢弘さんも、同じ話を顧客から聞いたことがあると教えてくれた。
「ミズナラ樽の風味は、思ったほど強くないということに驚かれるメーカーの方も多くいらっしゃいます。そもそもミズナラは他の樽材とは働きが異なり、熟成に長い年月が必要な樽材であることは間違いありません」
ジャパニーズウイスキーに詳しいウイスキーライターのステファン・ヴァン・エイケンは、さらに懐疑的な印象を抱いている。
「ほとんどのウイスキー愛好家は、誰かに教えてもらわない限りミズナラ樽原酒の香味をブラインドテストで識別できないはずです。ミズナラ樽の個性として語られるアイデンティティの多くは、誰かのそれらしいストーリーを通じて形作られてきたものだと思っています」
それでも適切な木材を選んで正しく処理し、正確に樽を組み上げ、しっかりと長期にわたって熟成すれば魔法はしっかり現れる。すべての条件が調和したとき、ミズナラ樽熟成の結果は驚くべきものになるのだ。ステファン・ヴァン・エイケンは、心に深く刻まれている2つの例を挙げてくれた。
そのひとつは「山崎50年」の第1回リリース。もうひとつは名古屋のバー「バーンズ」のために瓶詰めされたシングルカスクの「山崎」(オーナーズカスク)だ。どちらも100%ミズナラ樽熟成のウイスキーである。ヴァン・エイケンが、味わったときの感動を思い出して語る。
「バランスと深みがあり、まるでミズナラの香りそのものを体感するようでした。まさに身体全体で共鳴するような印象があり、長大な時間そのものを味わうような体験だったのです」
ミズナラ樽熟成の見極め方
ベンチャーウイスキーの秩父蒸溜所では、ミズナラ樽の将来について熱心な研究が進められている。世界中のウイスキーメーカーに樽を販売している有明産業とは異なり、秩父蒸溜所は自前で樽を製造しているメーカーのひとつだ。同社専属の樽職人でもある宮澤一揮さんが説明する。
「秩父蒸溜所では、ミズナラ樽の製造を2015年頃から開始しました。私がこの仕事に携わったのは2020年からです」
秩父蒸溜所の場合、ミズナラの原木は北海道から調達し、多くの場合は広葉樹丸太市などで購入している。入札の前日までに、木目や節の位置、樽材にしたときの強度などを確認して1 本ずつ厳選するのだと宮澤さんは言う。
「ミズナラはチローズの含有量が少ないんです。チローズはアメリカンオークに多く含まれ、樽材の気密性を高めてくれる成分です。チローズが少ないミズナラ材で造った樽は漏れやすいので、漏れを塞ぐために木製の釘を使うこともあります。場合によっては、樽材を部分的に交換したりしなければならないので大変です」
木材を曲げるのにも時間をかける。板は加熱してから数週間休ほどませて、曲がった形状を記憶させるのだという。こうすることで、樽を組み上げたときに樽材が割れる可能性を減らすことができる。
「現在、秩父蒸溜所で最も熟成期間の長いミズナラ樽原酒は9年ものです。最高の風味は20〜30年後に現れると言われていますから、その時まで願いを込めてゆっくりと熟成を進めています」
ミズナラはもはや日本だけのものではない。近年はスコットランド、アイルランド、アメリカ、デンマークの蒸溜所までが、その希少性やエキゾチシズムをアピールするためにミズナラ樽を使い始めている。
だがミズナラ樽熟成の真価を表現すべく真剣に取り組んでいるメーカーもあれば、そうではないメーカーもあるのが事実だ。ウイスキー評論家のデイヴ・ブルームが語る。
「ミズナラ樽熟成という触れ込みが、ギミックであるかどうかはすぐにわかります。熟成期間が表示されていなかったり、フィニッシュ(後熟)だけに使用していたり、スピリッツの特性を語らずに樽の付加価値ばかりを語っていたりしている商品は要注意ですね」
ミズナラはマーケティング担当者にとって魅力的な存在だが、そのミズナラの魅力を定義するのは極めて難しい。ミズナラは高価で、熟成に時間がかかり、結果の予測が用意ではないからだ。
しかし新製品が次々と発売されるウイスキー業界で、ミズナラの魅力はあまりにも大きい。ブランドのイメージに深みを加え、ミステリアスな物語を想像させてくれる存在なのだ。その物語は、いつか現実のものとなることもあると有明産業の坂本さんは言う。
「ミズナラは、単なる木ではありません。その本質は、ミズナラ樽でウイスキーを熟成するという一連のプロセスにこそあります。適切な木、適切な熟成、熟練の樽職人、そして長い時間が加わって、初めてミズナラ樽の真価が発揮できます」
その長い時間について、交渉の余地はまったくない。ミズナラは仕事の効率化に報いてはくれないし、どんな近道も許さない。多くのウイスキーメーカーが欲しがる静謐な香りは、注文通りに引き出せるものでもないのだとデイヴ・ブルームは語る。
「ミズナラは謙虚さを教えてくれる存在です。誰もがミズナラと正面から向き合って、一緒に仕事をしていく必要があるのですから」
これがミズナラの真の魅力だといえるろう。ミズナラは、風味だけでなく哲学もウイスキーに与えてくれる。忍耐を貫くことの美しさも教えてくれる。決して急ぐべきではないこと、美はしばしば目に見えないところに隠れていること、最も力強い物語は時間をかけて育つここと。そんな世界の秘密をウイスキーメーカーに思い出させてくれる存在なのだ。
待つことを厭わないウイスキーメーカー、樽職人、ブレンダーたちにとって、ミズナラは長い付き合いの果に報いてくれるかもしれない存在だ。それは簡単に説明できるような風味ではなく、より静かで、より深く、そして最終的には永続的な輝きをもたらしてくれる。