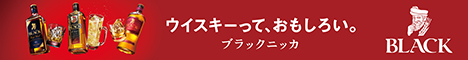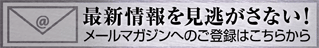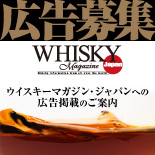北欧のウイスキー生産者たちが連帯する理由【後半/全2回】

産地ブランドの隆盛は、個々のメーカーの利益にも直結する。北欧における同業者の連帯は、世界中のウイスキー業界に貴重なヒントを授けてくれる。
文:ヘザー・ストルゴー
現在のウイスキー業界が、困難な時期にあることは否めない。ノルディックウイスキー界の寵児として名高いマクミラ蒸溜所(スウェーデン)が、昨年に破産申請したのは衝撃だった。その後も、北欧のさまざまな蒸溜所が困難な状況に直面している。そのひとつが、ライ麦を主原料とした自社製品を「ライウイスキー」と名乗れなくなる問題だ。
ライ麦は、北欧諸国の重要な穀物として食文化を支えている。各地のスピリッツ蒸溜所も、ウイスキーに地元色を加える手段としてライ麦を積極的に採用してきた。直近の問題は、EUとカナダが2004年に結んだ貿易協定(多くの北欧の蒸溜所が設立される以前に締結されたもの)に盛り込まれた条項に起因する。
これはカナダ以外の産地で「ライウイスキー」が名乗れなくなるという極めて大きな問題で、解決の糸口を探るために北欧諸国の蒸溜所が互いに連携をとっている状況だ。
今年の4月1日には、スタウニング(デンマーク)やキュロ(フィンランド)などの大手ブランドが連携してSNSキャンペーンを開始し、この問題を浮き彫りにした。あえてエイプリルフールに行動を開始したのは、問題の規則が荒唐無稽な理路によってでっち上げられたという皮肉を込めたかったからである。
新しい規制にあわせて、ラベルの記載内容やデザインは各社が刷新している。それと同時に、北欧のウイスキー業界は結束して前進の道を探り続けている。カナダのナイアガラ短大で蒸溜技術を教えるアンドレア・フジャルチュク教授が、同業者が連帯することのメリットについて次のように指摘している。
「消費者はある種の集団に対して、当然のように共通点を見出して一般化しようとします。特に『高級品』『消費財』『信用財』といったカテゴリーに属するウイスキーのよう製品では、その傾向が顕著になります。だから北欧産のウイスキーをひとつのカテゴリーとして打ち出すのは理にかなっているのです」
フジャルチュク教授は、ウイスキーに対する消費者の認識を研究中だ。これまでの調査から、世界各国のウイスキー産地が独自基準を設けることでブランド価値を保護しようとする動きに自然な関心を抱いている。
そもそも北欧諸国には、高品質でプレミアムな製品のイメージがある。だがそのようなイメージやブランドを繁栄させるには、さらなる努力も必要だとフジャルチュク教授は言う。
「近隣の蒸溜所は、いつも競合関係にあります。それでも最終的には、共同で評判を確立するために協力しなければならなりません。その協力がうまくいったら、次は定められた共通の基準を維持しながら革新を許容し、意図しない障壁を回避する方法について合意を形成し、産地ブランドへの信頼性を維持するための方策を模索する必要があります」
この考えを実践に移している一人が、オーロラ・スピリット蒸溜所の共同創業者であるトル・ペッター・W・クリステンセンだ。
「同業者である我々が、互いに競合関係にあるのは確かなことです。でも実際には、みんなの協働を通じてお互いを高め合っているんです」
産地ブランドの隆盛から得られる多大なメリット
クリステンセンは、協力団体である「ノルスケ・デスティレリ(ノルウェー蒸溜所協会)」の活動にも時間を割いている。この団体は2024年にノルウェーのクラフト蒸溜所各社を代表する組織として発足し、ノルウェー全土のスピリッツ生産地をカバーしている。ノルウェーの国土は南北に長く、オスロ周辺の温暖な農業地帯から北極圏まで気候も多岐にわたる。
クリステンセンは同僚のソールサンドと情報を共有することで、北欧全体における同業者の考えや動向にも精通しているようだ。
「一言で協働といっても、階層があるんです。国内団体は国内問題に焦点を当てられるし、ノルディック・ウイスキー・コラボレーションはウイスキー産地として北欧全体の発展を広く支えられますから。たとえばノルウェーの蒸溜所には、自社施設内でウイスキーを販売できないという規制の問題があります」
インギエル・ソールサンドも考え方は同じだ。
「ノルディックウイスキーの多様性にも、人々の目を向けさせたいと願っています。実に多彩なスタイルがあるのですから」
蒸溜所ごとの独自性を打ち出しながら、地域全体のプロモーションを図るのは、一見すると矛盾した行動のように思われるかもしれない。だがソールサンドは、それが合理的な行動なのだと明確に説明する。
「消費者はスコッチウイスキーをスコットランド産だと容易に認識できます。そうやって産地に関連する特徴を商品の個性に結びつけて考えているのです。北欧でも同じことができたら、メリットがあるに決まっています」
北欧諸国の多くは税率が高く、酒類販売店は政府によって規制され、広告規制も厳しいという共通点がある。どの国も、ウイスキー産業の発展に有望な市場とは映らないかもしれない。しかし改めて内情を分析してみれば、農業が盛んで清らかな天然資源とも共存していることがわかる。
もともと優れたウイスキーの基盤がここにあって、ずっと注目されるのを待っていたのだ。そして地域の特性を生かした風味や技術を確立させ、新たな道へと導いてくれる好奇心いっぱいの人々もいる。新北欧料理(ニュー・ノルディック・キュイジーヌ)の理念は、かれこれ20年以上も前から育ってきた新しい伝統だ。これをアルコール飲料の世界にも展開するのは、とても自然な流れともいえる。
もちろん蒸溜所ごとに、発信したい物語は異なることもあるだろう。だがここに住む人々、大地の特性、積み上げてきた歴史、そして素晴らしい風味という魅力が横のつながりを持ったとき、そのネットワークは多くの人々の胸を躍らせてくれる。チューウイスキーのヤコブ・ステルンホルムは、対話の終盤で次のように語ってくれた。
「結束することで、我々はもっと強くなれるんです」
スティエルンホルムは、事業を始めてすぐにこの認識を持てたのだという。ウイスキー製造という新しい伝統を維持し、さらに発展させるための行動を起こす情熱こそがコミュニティの力である。