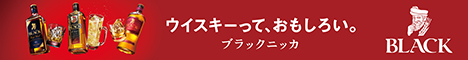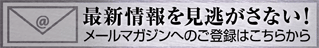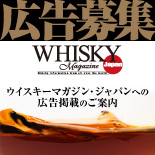アンソニー・ウィルズとキルホーマンの20年【第2回/全3回】
 火災からの復活とファーム・トゥ・ボトルの理想。コアレンジの確立によって、キルホーマンの夢がついに現実となる。
火災からの復活とファーム・トゥ・ボトルの理想。コアレンジの確立によって、キルホーマンの夢がついに現実となる。聞き手:ステファン・ヴァン・エイケン
初年度に蒸溜したスピリッツは、樽にして数本分でしたね?
2005年の生産量はわずか樽7本で、そのうち5本は個人のお客さまに販売しました。ウイスキーを製造する前から、樽単位で原酒を予約販売していたのです。でもこの方法にはリスクもありました。当時はもっと早期から生産が開始できるだろうと考えていたので、2005年初頭に「春には生産開始予定」と伝えて樽の購入を呼びかけたのです。実際には約束を破ることになってしまいました。
とにかく何らかの収入源が必要だったため、個人向けにシングルカスクを事前販売することで、同時にキルホーマンの宣伝になるという思いがありました。でもご想像の通り、風当たりが強かったのも確かです。まだ完成していない蒸溜所のウイスキーを買うのは勇気が要りますから。「蒸溜所すら建設せず、ウイスキーも製造しなかったらどうしよう」と懸念していた購入者もいたようです。
最初期のスピリッツ貯蔵にはファーストフィルのバーボン樽を選ぶ蒸溜所が多いなか、リフィルのバーボン樽を選んだのはなぜですか?
最初期の樽は誰にも販売するつもりがなかったので、リフィル樽に入れようと以前から考えていました。リフィル樽なら、長期熟成が可能になるからです。熟成はおそらく25年弱くらいで完了するだろうという見込みで、スペイサイドクーパレッジから15〜20本のリフィル樽を購入して最初期のスピリッツを貯蔵しました。
現在は農場内で栽培大麦のモルト(つまり100%アイラ産)が生産量の約3分の1を占め、残りはポートエレン製麦所から購入されています。当初はすべて自前の農場で賄う計画だったのに、それが叶わなかったのは2006年2月12日に起きた火災のせいですか?
その通りです。ただし100%自前の大麦モルトが実現できるという考えは、そもそも自分の見込みが甘かったとも思っています。
火災の経緯について、あらためてご説明いただけますか?
アイラでは、ボウモアとラフロイグがフロアモルティングを実践しています。彼らからも、必要な工程や設置すべき設備について大まかな説明を受けていました。しかし資金が逼迫していたため、設備が不完全なままフロアモルティングを始めました。
具体的には、適切な乾燥システムを導入していなかったのです。ピート処理後の麦芽を湿度4~5%にまで乾燥させる工程で、無煙炭を使うことにしました。でもこれが本当に無謀な選択でした。無煙炭は適切な温度を保つのが難しく、極度な高温状態や温度不足が起こりがちだからです。
フロアモルティングには膨大な労力を要しましたが、私と蒸溜所長のマルコム・レニーだけで管理していました。ある週末、息子のピーターと私は真夜中に炭を焚いて、床に敷いた麦芽の層をひっくり返す作業に出向きました。キルホーマンでは積まれた麦芽が分厚い層をなしているので、上層が湿ったままなのに下層は焼け焦げるほど乾きます。均一に乾燥させるため、十分な掘り返しが必要なのです。
そして気付いたら、キルンが炎上していたのですね?
そうなんです。火災があって良かったとは言いませんが、やり方を見直す機会となりました。適切な乾燥システムが必要だと気づき、温風乾燥システムを導入したのです。依然として大麦の投入量は多めですが、以前よりはうまく乾燥できるようになりました。自社製麦における最大の問題は、乾燥の不均一から生じる収率の低さです。この経験から大きな教訓を得ましたが、適切な助言をくれる人はほとんどいませんでした。
実はキルンが火事になる以前から、自社製麦の大麦を補うためにポートエレン製麦所から麦芽を購入しようと決めていました。完全な「ファーム・トゥ・ボトル」を自社で完結させるのが夢ではありましたが、すべての原料を自社で栽培加工することが現実的ではないと気づいたのです。
すでにブルックラディ蒸溜所がアイラの農家の大半と契約を結んでいたので、他の農家から麦芽を確保するのが困難だとわかって考え直したのです。むしろ自社農場の麦芽だけでつくったシングルモルトを「シングルファーム」の商品で表現し、残りは製麦業者から調達した麦芽で補った方が、今後の展開として適切だろうと判断しました。
ポートエレン製麦所のヘビーピーテッド(50ppm)麦芽と自社農場のミディアムピーテッド(15〜20ppm)麦芽は、生産ラインも明確に区別しています。異なったスタイルにして、明確な違いを表現したかったのでそうしました。
日本の多くのウイスキー愛好家にとって、キルホーマンとの最初の出会いは「ブランブルリキュール」でした。なぜこのリキュールをつくったのですか?
蒸溜所が動き出してから、2006年から2008年にかけて世界中を回りました。ニューメイクスピリッツをボトリングして、世界のファンや関係者に味わっていただき、シングルモルトの熟成が完了した際にはぜひ購入していただけるよう土台作りに努めていたのです。
「ブランブルリキュール」は、主に蒸溜所直営店での販売を目的に製造しました。キルホーマンのスピリッツを原料に、スコティッシュ・リキュール・センターで製造した高品質なリキュールです。蒸溜所を訪れるお客さまの多くがお求めになるほどの人気は予想していませんでした。でも世界中からブランブルリキュールの需要が急増したので、あわてて輸出を開始したのです。
その後、スコティッシュ・リキュール・センターが製造の継続をやめることになって終売しました。自社での製造も検討しましたが、既存の業務に支障をきたので見送りました。多くの方々に愛されていたので、頑張って継続すべきだったのかもしれません。でも当時は他のことで手一杯でした。
そして2021年に「マキヤーベイ」、その3年後に「サナイグ」が発売されました。現在はこの2銘柄がコアレンジの柱となっていますね?
2009年9月9日に初めてのシングルモルトを発売した後は、3年熟成、4年熟成、そして5年熟成(少量)と小規模な限定版のリリースを続けてきました。いずれも12,000本までの限定商品です。世界中に配分しようと試みましたが、こうした限定版ばかりリリースするキルホーマンの方針に不満を抱かれた方も多かったようです。ブランド認知度の向上には寄与しましたが、やはり中核となる製品の開発が必要でした。
「マキヤーベイ」は主にバーボン樽で熟成させています。実をいうと、今年初めに原酒の構成比率をわずかに変更しました。従来はバーボン樽90%にオロロソシェリー樽10%という構成でしたが、現在は80:20となってオロロソ樽の影響が少し強まっています。熟成期間も徐々に延長していますが、その変化のペースはかなり緩やかなものになるでしょう。
この「マキヤーベイ」には、素晴らしいレモンのような柑橘と甘い花の香りがあります。実際の熟成年数を超えた完成度です。とても柔らかな口当たりで、フルーティで飲みやすく、スピリッツの強さは感じられません。活き活きとした若々しい印象ながら、他にない独自の個性を備えています。これは蒸溜器から生まれるスピリッツ自体の特性にも大きく起因しています。
後発の「サナイグ」は、良き友人であるティエリー・ベニタ(ラ・メゾン・デュ・ウィスキーCEO)との会話から生まれました。ティエリーが「マキヤーベイと並べて棚に置ける主力商品がもうひとつ欲しい」と言ってくれたのです。サナイグは主にシェリー樽で熟成されるため、シェリー樽の影響が強く感じられます。「マキヤーベイ」ほどの人気は想定していませんでしたが、市場によっては「マキヤーベイ」の売上を抜いています。価格帯はやや高めですが、それで売れ行きが鈍ることもありませんでした。
「サナイグ」は、いわゆる「シェリー爆弾」ではありません。上品なシェリーの影響を感じさせつつ、塩気やピートの特徴がしっかり味わえるウイスキーです。バーボン樽の熟成によるクリーンでフレッシュなスピリッツの特徴が現れていますが、「マキヤーベイ」とはまったく異なる個性があります。
コアレンジの原酒構成では一貫性を重視されていますか? それとも微細な差異は許容されますか?
バッチごとに製造しているので、いつも完全に同一の製品がつくられるわけではありません。それでもレシピは確立しており、長年にわたって同じサプライヤーからバーボン樽とシェリー樽を調達しているので、品質の安定は保たれています。もちろん樽ごとにも微妙な差異はありますが、一般のクーパレッジから購入する場合よりもはるかに均一性は高いといえます。クーパレッジから調達すると、しばしば樽ごとに大きな違いが生じることもありますから。
それでも長期的に見れば、「マキヤーベイ」と「サナイグ」のレシピにも変更は加えられてきました。そのためバッチごとに多少の差異が生じています。特にサナイグはシェリー樽の影響を大きく受けるので、色や特性に多少の違いが出てくることもあります。
ウイスキーのスタイルがわずかに変化したことで、否定的なご意見をいただくことはほぼありません。かなりのレベルで一貫性を保てていると思いますが、大手メーカーのように完全な同一の味わいを維持しようとしていないことも事実です。それでも当然ながら、顕著な違いが生じないように細心の注意を払っています。
一部の限定商品には、熟成年数が表示されています。コアレンジ商品にも熟成年数を表示する予定はありますか?
消費者のみなさんの声に、耳を傾ける必要があります。各国市場に足を運ぶのは、各市場で「熟成年数を表示してほしい」といったご要望を直接うかがいたいから、その意味で、年数表示の重要性は理解しています。でも4年、5年、6年といった具合に、段階的な熟成年数を表示するアプローチには意味がないとも考えています。
最初期の原酒の在庫から、熟成年数を表示した限定商品はすでに発売しています。でも10年熟成の定番化を検討するのは、まだ先の話になるでしょう。コアレンジに10年熟成の商品が必須だと決めつけているわけではありませんが、品質の目安として年数表示を好む消費者が多いので導入する可能性はあります。年数表示が必須とまでは思いませんが、やはり目安となることは確かです。
年数表示のあるコア製品がないと、消費者のみなさんに理解していただくためにさらなる販売努力が必要になります。それでも今ではキルホーマンもさまざまな国の市場で一定の知名度を獲得しました。まさに日本がその好例です。キルホーマンは創設時から日本市場に参入しており、バーでも取り扱っていただけるようになりました。しかも片隅に1本だけ置かれているのではなく、複数銘柄が並んでいる様子を目にできるのはとても嬉しいことです。
(つづく)
キルホーマンをはじめ、個性あふれる世界のモルトウイスキーを網羅。ウィスク・イーのオフィシャルサイトはこちらから。