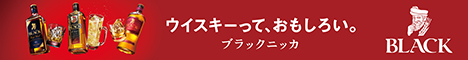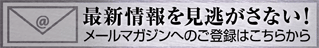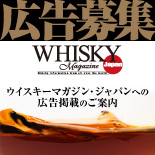アンソニー・ウィルズとキルホーマンの20年【第3回/全3回】
 急成長にあわせて増産し、コロナ禍と需要減退に直面。アイラとキルホーマンは、新しいウイスキーの時代を生きている。
急成長にあわせて増産し、コロナ禍と需要減退に直面。アイラとキルホーマンは、新しいウイスキーの時代を生きている。聞き手:ステファン・ヴァン・エイケン
ノンピートのスピリッツが2012年に製造され、数年にわたって数量限定でリリースされました。キルホーマンでノンピートのスピリッツを製造した経緯は?
実は2012年8月に乾燥炉が故障して、ごく短期間ですが自社農場で栽培した大麦をノンピートで製麦しました。その時に蒸溜したスピリッツの量は、樽にして75本分です。自社栽培の大麦は製麦工程を管理できるので、2012年以降も毎年わずかながらノンピートのスピリッツを継続的に生産しています。
以前はスピリットレシーバーがひとつしかなかったので、ピーテッドモルトのフェインツ(蒸溜時の残存液)も用いてノンピートを製造していました。だからごくわずかにピート香が残っていたんです。つまり「ノンピート」と謳いつつ、ほのかにピート香が残っていることを説明してご理解いただきました。
でも7年前にスピリットレシーバーを分けてからは、ノンピートのスピリッツだけ別途で管理できるようになりました。現在は年間で1ヶ月間ほどノンピートのスピリッツをつくっています。自社大麦の約10%よりも少し多いくらいの割合です。ノンピート原酒の生産も極めて有益であると考えているので、今後も少しだけ量を増やす予定です。
他の生産工程でも実験を盛り込んでいますか?
ときどきですが、実験はやっています。酵母を変えることで、スピリッツの特性に与える影響を検証してきました。またカットポイントを変えて蒸溜したスピリッツも製造しています。マッシュの排出速度にも変化を加えてみました。キルホーマンでは、心地よいフローラルな香りのスピリッツを得るために澄んだ麦汁を求めています。でも普段は30分かけるマッシュの排出を15分に短縮する実験もしてみました。すると麦汁が少し濁った状態になり、スピリッツの特性にも微かにはっきりとした違いが現れました。
しかし結局のところ、スピリッツは樽に詰められます。蒸溜器から取り出した時点では違いがあっても、樽の中で何年か熟成させるうちに、そのようなスピリッツの違いはかなり小さくなっていきます。だから実験を加えた原酒を選んでも、大きな違いを感じさせるわけではありません。確かに違いは存在しますが、大した差ではないのです。
さまざまな目新しい商品を次々と発表し、実験的な蒸溜所と見なされるのがキルホーマンの目的ではありません。目標はブランドを成長させることであり、それはコアレンジの定番商品によって達成されるからです。コアレンジ商品こそが、事業を推進する原動力になります。数量限定のリリースは市場ごとの割り当てが決められており、愛好家の方々にだけご満足いただくのが目的です。
バーボン樽70%、シェリー樽30%という創業期の樽熟成ポリシーは変化していますか?
樽の種別は、割合が変化しています。シェリー樽熟成を強調したスタイルへの需要が高まったため、シェリー樽の割合を増やしてきました。ピートの効いたスモーキーなスピリッツや、海っぽい塩味を感じさせるウイスキーにシェリー樽を使用するのは難しいだろうと思っていました。でもキルホーマンでは、とても良好な結果が得られています。そんな背景もあって、実際にシェリー樽の使用量は増やしています。
消費者のみなさんがシェリー樽熟成を好まれているのは承知していますので、現在ではバーボン樽60%、シェリー樽35%といった割合です。残りの5%は実験的な樽です。それでもやはり、バーボン樽が熟成でもっとも重要な役割を担っています。キルホーマンのスピリッツは、バーボン樽の熟成に極めて美しく調和すると考えられるからです。最近リリースした18年熟成のウイスキーや、10年以上熟成した限定商品を味わっていただけたら相性の良さがおわかりいただけるでしょう。
実験的に使用した樽で、キルホーマンのスピリッツに適さない樽はありますか?
アルコール度数が12~15%程度のワイン樽(非発泡性)は、扱いが難しいと思っています。ボルドーなどの赤ワイン樽で熟成された原酒は、口内にとてもドライな感触を残します。ウイスキーの熟成も十分に進まず、かなり不均一な熟成状態になります。ソーテルヌ樽はまずまずの成果でしたが、これは甘口でコクがあるためうまくいったのでしょう。過去20年間でわかったのは、アルコール度数が18~23%程度の酒精強化ワイン樽がキルホーマンのスピリッツと相性が良さそうだということです。
私は個人的に、ウイスキーの香味の60~70%が樽由来であるという説の信者です。だからいろんな樽で熟成してみる実験は大好きで、それもフィニッシュではなく最初からその樽で熟成するスタイルを追求したいと考えてきました。
ただし、このような実験に時間をかけすぎてはいけないという意識もあります。キルホーマンのスピリッツにぴったりの熟成方法を早期に見出さなければならないからです。ふとした思いつきが、間違いではなかったと証明されるのは嬉しい瞬間です。でもキルホーマンにとって、バーボン樽やシェリー樽以上に適した熟成樽はないだろうとも思っています。
実験的な樽熟成にまつわる課題は、新たに入手した樽のバッチが、前回のバッチと異なった特性を持っていた場合に一貫性が得られないこと。バーボン樽やシェリー樽が提供してくれる一貫性こそが、キルホーマンに必要なありがたい品質なのです。でも小規模な蒸溜所なので、革新的かつ独創的であることも求められます。だから今後も実験的な樽の使用は続けていきます。
新しいキルンとモルティングフロアが2018年に完成して、自社内の製麦機能が向上しました。しかしディアジオの方針で、ポートエレン製麦所からグループ外へのモルト供給が停止されます。キルホーマンや他のアイラの蒸溜所にどんな影響がありましたか?
ディアジオ傘下以外の蒸溜所にとって、これは共通の大問題になっています。フェリーの運航が不安定になっているのもご存じのことでしょう。ディアジオもPRに失敗したと自覚しているようです。ポートエレン製麦所が1980年代に建設された際、アイラの全蒸溜所に一定割合のモルト購入を義務付けました。しかし今になって、この慣行を継続しない方針を明確にしたのです。誰も詳細な理由はわかっていません。
いずれにしても、モルト調達のためにスコットランド本土と行き来する状況は、アイラのウイスキー生産者にとって重大な問題を引き起こしました。仕方がないので、今は本土の製麦業者を見つけて契約しています。アイラ島のピートは本土のピートとまったく異なるので、エディンバラ南部の製麦業者にアイラ産のピートを送って特性を維持しています。このような対応とは別に、不安定なフェリーの運航も深刻な問題となっています。
サステナビリティを追求してトラックでの輸送を減らしたいのに、逆に増加しているのも問題です。でもこの問題を回避するのは、アイラのどんな蒸溜所にとっても困難でした。それでも本土には製麦業者たくさんあるので、何とか対応できています。
今後もこの状態は続くのでしょうが、キルホーマンでは自前の製麦施設の建設計画を進めており、自動化された製麦所の建築許可も取得済みです。費用は安くありませんが、大麦を調達して敷地内で製麦します。また現在の市場環境が厳しい状況なので、この計画も一時保留としています。でもいずれは確実に実施する予定です。
2019年8月までにポットスチル2基とマッシュタン1槽を追加し、ウォッシュバックは6槽から14槽に増やしました。年間生産能力は65万リットルに達しましたが、さらに生産量を倍増させる計画が棚上げになった理由は?
2019年に生産量を倍増させたのは、そうしなければ2021〜2022年頃に在庫が厳しくなると予測できたからです。2022年は需要に追いつくのが困難だったので、その後に少し販売量の減少が見られたときはむしろホッとしました。ここでひと息ついて、再び在庫を積み増す余裕ができたからです。もし販売量が当時のペースのままだったら、全在庫を割り当てざるを得なかったでしょう。
2019年に増産し、2022年には再増産を決断しました。つまり年間130万リットル規模へと生産規模を拡大する計画です。ブランドの成長を継続させ、ウイスキーを供給し続けたいと考えていました。しかし需要の減速が発生した時点で、この計画を進めるのが賢明ではないと判断しました。明らかに、需要の減速は我々の予想以上に長期化しています。この状況は、おそらく2026年以降も続くでしょう。各国政府が対策を整理するまでは難しそうです。
バルバドスでラム蒸溜所を建設するプロジェクトの進捗状況は?
このプロジェクトは、2015年から2016年にかけて開始されました。息子のピーターが主導し、私も全面的に支援しています。これまでキルホーマンで成し遂げたことをカリブ海地域でも再現するのが目標です。ストレートでじっくり味わえる高品質なダークラムの需要が拡大してきました。キルホーマンの事業とも相性は良く、世界中に流通網も整っていたため、すべてが理にかなっていると考えて乗り出しました。
蒸溜所建設地のリサーチには時間がかかりましたが、2019年から2020年にかけてようやく見つけました。土地を購入し、計画の許可を得るまで1年半から2年を要しました。ところがその後、新型コロナウイルスが流行し、世界的なスピリッツ市場の低迷が続いて計画が一時保留となりました。土地は確保済みで、建築許可も取得済みです。許可には5年間の有効期間があり、必要に応じて更新もできます。現在は計画を再検討しつつ、どこから着手できるか模索中です。
スコッチウイスキー業界全体やキルホーマンの事業には、今後5年から10年先にどんな未来が待ち受けていますか?
あくまで私見ではありますが、業界再編が進むと予想しています。スコットランドだけでなく、世界中で新しい蒸溜所が急増しました。しかし新規参入の数は、必然的に縮小していくと思います。
ここ5年ほどで、たくさんの新しい蒸溜所がシングルモルト商品を発売してきました。そのため卸売業者は飽和状態です。蒸溜所は販路の開拓に努めますが、卸売業者はもうポートフォリオが飽和状態で、新たなブランドの受け入れに消極的。小売店やバーも同じ課題を抱えています。純粋に棚のスペースが不足しているのです。
どの蒸溜所も優れたウイスキーを製造しているのは間違いありませんが、それだけで差別化は図れません。だからこそキルホーマンが適切な時期に蒸溜所を建設し、18年間にわたって着実に市場でのポジションを成長させ、小規模ながら世界的なブランドを確立できたことに心から安堵しています。
今から2013~14年以降に操業を開始した新規蒸溜所の立場にはなりたくありません。現在の状況はかなり厳しく、業界全体が悲観的な見通しに覆われるのを目の当たりにしています。スコットランドのウイスキー生産量は大幅に減少しました。さまざまな蒸溜所で数百万リットル単位の減産があり、なお過剰生産の状態に陥っています。こうした事態は過去にもありましたが、前回は80年代のことでした。そして現在は誰もが「80年代よりも深刻だ」と口にする状況です。
この状況がどのように収束し、5年後や10年後にどんな展開を見せるのかは予測できません。それでもキルホーマンの未来に限っていえば、蒸溜所が確固たる基盤を築いてきたことに自信を持っています。この嵐を乗り切り、やるべきブランド構築に黙々と専念するのみ。シングルモルトウイスキー市場は、いずれ必ず回復することでしょう。それでも現在は非常に厳しい状況です。
アイラではアードナホー蒸溜所が2018年末に生産を開始し、ポートエレン蒸溜所が昨年から操業を再開しました。建設中の新しい蒸溜所も数軒あります。アイラという地域ブランドは、難局を乗り切る有利な条件になりますか?
アイラという所在地の威光は、確かに助けになるでしょう。でも正直なところ、キルホーマンの次の蒸溜所がアイラで建設されるまでに、とても長い時間がかかりましたね。アードナホー蒸溜所はキルホーマンから12年遅れで設立されました。現在ではラガンベイ蒸溜所やポートナーチュラン蒸溜所が建設中で、来年中には生産を開始するとうかがっています。
アイラのブランドは確かに有利です。でも率直に言って、現在のアイラにはもう十分な蒸溜所が存在します。これは主に、物流上の理由を踏まえた見解です。アイラのウイスキー業界は、増えた蒸溜所の運営や雇用を支えるのに必要な投資を受けていません。それにもかかわらず、当局がなぜ計画許可を出し続けているのか、私にはまったく理解できないのです。政府による投資不足が原因で、アイラ内部ではさまざまな問題が生じているのですから。
最後の質問です。無人島で余生を過ごすなら、持っていきたいキルホーマンのボトルを3種類挙げてください。
蒸溜所に関わる全員が、大麦の生産からボトリングまでの全工程を自主管理した「100%アイラ」のリリースに誇りを持っています。まず自分用に1本選ぶなら、最近の20周年記念カスクリリースから「キルホーマン14年 シェリーカスク」。個人的にシェリー樽の大ファンというほどでもありませんが、これは私にとって特別な一本です。軽やかで花のような香りがあり、シェリー樽の風味が強すぎない点も素晴らしい。繊細でバランスの取れた味わいですね。
そして2本目は、最新の「キルホーマン 100%アイラ 15thリリース」。バーボン樽で熟成されたキルホーマンが大好きなのは、9年程度の熟成期間で最高の状態に達するからです。
最後の1本は、昨年コアレンジに加わった「キルホーマン バッチストレングス」でしょうか。個人的にカスクストレングスのウイスキーの大ファンです。度数が高すぎると言う人には「そう? じゃあ自分でちょっと加水したら」とお答えしますね。
キルホーマンをはじめ、個性あふれる世界のモルトウイスキーを網羅。ウィスク・イーのオフィシャルサイトはこちらから。