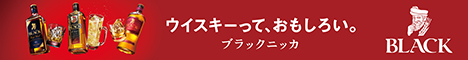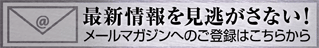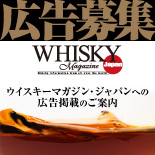アンソニー・ウィルズとキルホーマンの20年【第1回/全3回】
 今年で創立20周年を迎えるキルホーマン蒸溜所から、創設者のアンソニー・ウィルズが来日。稀有な挑戦の背景を語り尽くすロングインタビュー。
今年で創立20周年を迎えるキルホーマン蒸溜所から、創設者のアンソニー・ウィルズが来日。稀有な挑戦の背景を語り尽くすロングインタビュー。聞き手:ステファン・ヴァン・エイケン
前回の来日から、お久しぶりの東京ですね。
最後に日本を訪れたのは、12年前だったと思います。2008年から2013年までは、毎年のように来ていました。三男のピーターが事業に加わってから、ピーターが代わりに日本を訪ねるようになりました。久しぶりの日本を楽しんでいます。
数年前に、アイラでキルホーマン蒸溜所を訪ねました。アンソニーさんは、いつも現場で働いているタイプの創業者というイメージです。毎日の蒸溜所運営についても、自分の手を動かすのがお好きですか?
おっしゃる通りです。創業当初は従業員も少なく、蒸溜や製麦なども自力でやっていました。つまり最初からプロジェクト全体を管理していたのです。コンサルタント技師を雇ったり、ジム・スワンさんにスピリッツの特性に関するアドバイスを受けたりしましたが、私自身も製造工程には深く関与していました。
創業した2005年の当初は、わずか5名の従業員でスタートしています。私と妻、蒸溜所オペレーター(当時のマネージャーであるマルコム・レニー)、そしてカフェの女性スタッフ2名というメンバーでした。小さく始めたので、われわれ夫婦が手を動かし、事業のあらゆる側面に関わっていました。
私は創業の前年の2004年からアイラに居住しています。現地に常駐して、ウイスキーづくりに深く関与できた経験はとても役に立ちました。そもそもこの事業の性格上、現場から離れて指揮するのは難しい。現場に出ることでスタッフの役にも立てるし、私自身にとっても大きな意味があります。いつも現地にいることで、何か問題や課題が生じた際にすぐ解決策を講じられるからです。
現在は何人で蒸溜所を運営されていますか?
従業員の数は、急速に増加していきました。新しいビジターセンターを建設してからは、ますます多くのスタッフが必要になりました。エディンバラの営業所を含めると、観光シーズンは総勢で約47名が働いています。アイラでは雇用者数で第3位のウイスキーメーカーになりました。ブルックラディ蒸溜所とディアジオ(蒸溜所3軒とポートエレン製麦所を運営)に次ぐ従業員数です。
キルホーマンが設立される以前の90年代後半に、アイラのウイスキー業界は2人の偉人を迎えました。アンソニー・ウィルズさんとマーク・レイニエさんは、どちらもイングランド人でワイン業界の出身。アンソニーさんがワイン業界からウイスキー業界へ転身されたきっかけは?
私がアイラにやってきたのは、家族と一緒にスコットランドへ移住したいと思いが強かったからです。妻キャシーの両親が、引退後にアイラ島に住んでいました。その近くにいたかったというのが本当の理由ですね。
ウイスキー業界にも知人はいましたが、ワイン業界でのキャリアにも激変がありました。ちょうど英国のワイン業界全体で、スーパーマーケットが台頭しつつあったのです。当時はフランス企業の営業部長として、フランス各地の生産者を担当していました。でも独立系の小売店や一部の大手全国チェーンが次々と撤退し、スーパーマーケットが市場を席巻したことで意気消沈しました。スーパーマーケットとの取引は、決して楽しいものではありません。価格競争ばかりで、製品の品質も私が望むほどには重視されませんでした。
そんな経緯もあって、私たちは1995年に家族でアイラ島への移住を決断しました。当時は3人の息子たちも10歳、8歳、6歳と幼かったのですが、新たな一歩を踏み出すのは今だと思い切ったのです。ワイン業界から、別の業界への転身を考えていました。ウイスキー業界の知識はあったものの、当時はまだ関わりがありません。それでも参入するのに絶好のタイミングではありました。マーク・レイニエさんは、おそらく私と違う動機でアイラに来たのだと思います。私が独立系ボトラーとして活動を始める1〜2年前から、独自にウイスキーをボトリングされていましたから。
ウイスキーブーム以前の時代ですが、90年代後半に独立系ボトラーを始めるのがなぜ絶好のタイミングだったのでしょうか?
私が独立系ボトラーとして参入したのは、1995年から1996年頃です。絶好のタイミングと言ったのは、その数年前から独立系ボトラーがシングルカスクのボトリングを始めていたからです。ブレンド主体だった以前の役割から一転し、短期間で市場のプレミアム層を惹きつけていました。ダグラスレインやゴードン&マクファイルが先行して、シグナトリーヴィンテージも90年代後半から参入しました。
独立系ボトラーがマッカランやボウモアといった有名ブランドの樽を購入し、その蒸溜所名をラベルに記載したシングルカスク商品を販売する。そんな発想は、人々の認識を変えました。ウイスキー愛好家たちがこの流れを受け入れ、業界に変革が訪れたのです。小規模な独立系の企業が、業界の地図を塗り替えた驚くべき時代でした。
ダグラスレイン、ゴードン&マクファイル、シグナトリーヴィンテージといった老舗企業は、豊富な在庫があって原酒購入の資金も備えています。でも私はそうした基盤がないまま、一人で事業を運営していました。そのためウイスキーのロットを確保するのが難しく、潤沢な在庫を保有したこともありません。日銭を稼ぐように、樽20~30本ほどを購入しては市場に供給するという事業でした。
このような業界の変化に、やがて大手の蒸溜所が気づきます。自分たちが製造したウイスキーをブローカーに安価で売却すると、それを独立系ボトラーが買い取ってボトリングし、そのウイスキーが市場のプレミアムセグメントで流通する。こんな状況は、大手メーカーにとって不愉快だったでしょう。そして2000年代初頭には、蒸溜所からの原酒供給が制限され始めたのです。
販売が容易な有名蒸溜所のブランドから、原酒の供給がストップされ始めました。それでも私はまだテイスティングなどの地道な販促イベントなしでウイスキーを販売できていました。ハイランドパークやリンクウッドなどの原酒はまだ入手可能で、愛好家たちはこれらの蒸溜所のシングルカスク商品を飲みたがっていたからです。品質に多少ばらつきはあるものの、独立系ボトラーは全体として高品質なウイスキーを発売していました。しかし一部の蒸溜所から供給が止まり始めると、セカンダリーブランドの販売も難しくなってきます。なにしろ当時の私は、独立系ボトラーとして無名でした。でも行き詰まったところで、簡単な解決策があることに気付いたんです。自前の蒸溜所を建設すればいいじゃないかと。
自分で蒸溜所を建設せず、既存の蒸溜所を買収してオーナーになる道もありましたよね?
その路線も検討しましたよ。1990年代後半から2000年代初頭にかけて、グレンスコシア蒸溜所の買収を検討したことがあります。でもグレンスコシアはやや老朽化が進んでおり、しかも提示価格が予算を大幅に上回っていました。それよりも、やはり私は独自の道を歩んでゼロから始めたいという気持ちが強かったんです。
馬鹿げた計画だと思われることはわかっていました。アイラ島で120年以上ぶりに新たな蒸溜所を建設する計画です。当時の前例といえば1995年に設立されたアラン蒸溜所(現在のロックランザ蒸溜所)くらいで、私はその10年後の2005年に蒸溜所を建設しようしていました。周囲の大半は気が触れたと思ったようで、計画についても懐疑的でした。アイラの人々も口では励ましてくれるものの、内心では「莫大な資本が必要だから蒸溜所なんて建設できないだろう」と思っていたようです。
マーク・レイニエさんがブルックラディ蒸溜所を買収したのは2000年末です。もしマークさんより数年早く行動を始めていたら、ブルックラディ蒸溜所の買収に関心を抱いていた可能性はありますか?
その可能性はあったでしょう。でも当時の市場動向を踏まえると、むしろ新規蒸溜所の設立の方が有利だとも考えていました。既存の蒸溜所を引き継ぐより、自分が望むスピリッツをつくり上げるべきだと思っていたからです。既存の蒸溜所を買収したら、設備を一新しない限り、初日からその蒸溜所の特徴を継承しなければなりません。だから自分のやり方で、ゼロから蒸溜所を建設できたことに満足しています。蒸溜所を建設する唯一の利点は、白紙の状態から始められること。逆に言えば、他のメリットなどありません。財政的には明らかに大きな負担でした。
アイラ島で2005年に蒸溜所を建設するまで、どんな苦労がありましたか?
資金調達がまったく進みませんでした。まさに悪夢のような状況です。新しい蒸溜所への投資は、資金回収までの期間が長いので誰も関心を示してくれませんでした。でも純粋に利益だけを追求する人々に支配されるのは嫌なので、投資会社からの出資は避けたい。そこで同じ志を持つ人々を探し、個人投資家からの資金調達を目指しました。
資金調達には3年かかりましたが、それでもまだ足りません。そこで私は大きな賭けに出ました。蒸溜所の建設と数ヶ月間の運営に十分な資金が揃ったところで見切り発車したのです。ここまで来たのだから、諦めるのはあまりにも惜しい。あとは追加資金の調達で乗り切ろう。同じ状況になったら、資金調達のリスクを背負う人は多いと思います。すでに大きすぎるリスクを背負っていたし、家族の全財産を投じていました。限界を超え、すべてを賭けたことで腹が決まったのだと思います。
蒸溜所の建設地はどうやって見つけましたか?
アイラに土地勘があり、ロックサイド農場を所有するフレンチ夫妻(マーク・フレンチさんとロヘイズ・フレンチさん)と知り合いだったことが助けになりました。マーク・フレンチさんは、まだ私たち家族が休暇でアイラを訪れていた頃からの知り合いです。夫妻で30年近く農業を営んでおり、お子さんたちも私の息子たちと同世代でした。
マークさんに蒸溜所の構想を打ち明けたところ、とても好意的に受け取ってくれました。アイラの農家にとっては、農業経営を多角化できるチャンスだからです。彼らに追加収入の機会を提供しつつ、廃墟同然の建物を引き継ぐつもりでした。だからフレンチ夫妻にとっても、すべてが魅力的な提案だったのです。そんな経緯もあって、場所はわりと簡単に見つかりました。
この場所に決めたもう一つの理由は、ロックスサイド農場がアイラで最高品質の麦芽用大麦を栽培していたことです。アイラが理想の穀物産地とはいえません。それでもマークさんは優れた麦芽用の大麦品種を育てていたので、ウイスキー原料の条件を満たしていました。そして農場と一体になったファームディスティラリーの構想が形になっていったのです。
キーパーソンの一人であるジム・スワン博士は、プロジェクト初期でどのような役割を担われたのでしょうか?
親しくしていたウイスキーライターのチャーリー・マクリーンに電話をかけ、誰かアドバイザーを紹介してくれないかと尋ねました。するとチャーリーは言ったんです。「適任者はただ一人、ジム・スワン博士だ。とても現実的な人で、専門用語で煙に巻いたりせずに話を聞いてくれる。彼よりウイスキーづくりに詳しい人はいないよ」と。
そしてジムさんと面会しました。ちょうど彼が前職のタトロック&トンプソン社を離れ、自身のコンサルティング事業を立ち上げた頃です。独立したジムさんにとって、私たちはプロジェクト全体の構築を依頼した最初期の顧客になりました。残念ながら2017年に他界されましたが、まさに蒸溜所設計のキーパーソンでした。
設備の種類や仕様は、すべてジム・スワン博士と相談しながら選んだのですか?
その通りです。まず生産量を問われて「年間10万リットル」と答えました。スピリッツのスタイルは「アイラらしいスタイルにしたいけど、5年や10年も熟成を待っていたら事業が成り立たないので、比較的早期からボトリングしたい」と説明しました。製造に関する知識はまったくなかったので、スピリッツのスタイルについて話し合った後はすべてジムさんに一任しました。
当初は2005年5月末のアイラ・フェスティバルにあわせて蒸溜を開始する計画でしたね?
そうなんです。でも期限には間に合いませんでした。実際に稼働を開始したのは同年の11月末で、最初にニューメイクスピリッツを樽詰めしたのは2005年12月14日のことでした。
(つづく)
キルホーマンをはじめ、個性あふれる世界のモルトウイスキーを網羅。ウィスク・イーのオフィシャルサイトはこちらから。