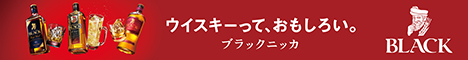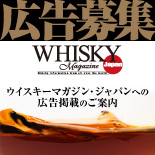雲上の井川蒸溜所を訪ねて【前半/全2回】
 秘境という言葉に、まったく誇張はない。日本有数の奥地に井川蒸溜所を訪ね、稀有なウイスキーづくりの真髄に触れる2回シリーズ。
秘境という言葉に、まったく誇張はない。日本有数の奥地に井川蒸溜所を訪ね、稀有なウイスキーづくりの真髄に触れる2回シリーズ。文・写真:ステファン・ヴァン・エイケン
今から6年前といえば、日本国内で次々に新しいウイスキー蒸溜所が開業していた頃だ。だが2019年初頭に参入を発表した新しいメーカーは、日本のウイスキー業界を少なからず驚かせた。
クラフトディスティラリーの設立も、小規模なウイスキー蒸溜所のプロジェクトも珍しくはない。だがウイスキー製造を始めるのは、すでに飲料業界で活動している企業が多かった。だから井川蒸溜所の運営元が、製紙業の企業であるというニュースは新鮮だったのである。
だが背景をよく調べてみると、実はそれほど驚くべきことでもなかった。蒸溜所を設立する企業とは、特種東海製紙株式会社だ。創業者の大倉喜八郎は、明治時代を代表する実業家である。
大倉は1895年に南アルプス南部の森林に24,430ヘクタールの土地を購入して製紙業を営みはじめた。この事業は紙製品の製造、加工、販売に特化した主要企業の特種東海製紙株式会社に成長している。井川の森林は日本最大の私有地であり、日本の森林面積の千分の一を占める。世界有数の森林率(約67%)を誇る日本で、これは特筆すべき数字であろう。
特種東海製紙は、サステナブルな事業活動を通じて地域の活性化に取り組んでいる。その一環として、新事業としてのウイスキー製造が2017年頃から提案されていたのだという。社内での検討を経て経営陣に承認され、2020年4月には完全子会社の十山株式会社が設立された。十山は森林の管理、ウイスキーの製造販売、森林内でのエンターテインメント施設や宿泊施設の開発などを担当する。
ウイスキー蒸溜所の設立は、むろん容易な事業ではない。とりわけ山間部の僻地となれば、並外れた胆力と将来への見通しが不可欠である。井川蒸溜所は、当初2020年7月までに本格的に生産を開始しようという計画だった。しかし大雨による道路の寸断で、大幅な遅延が発生する。ようやく蒸溜を開始する準備が整ったのは、同年10月のことだった。
その後、井川蒸溜所のチームはさまざまなウイスキーイベントに顔を出すようになった。熟成の途上にあるウイスキーの試飲キットを携え、その頻度も年を追うごとに増えてきた。数年間の待機期間を経て、私自身も蒸溜所を訪れてみたいという思いがいよいよ強まってきた。
そして今年3月下旬に、蒸溜所訪問の手筈が整った。しかし運悪く、再び大雨と土砂崩れによって3月中の訪問計画は流れてしまう。仕切り直して6月中旬、ようやくすべての準備が整って現地に乗り込むことになった。
井川蒸溜所への訪問を「大遠征」と称するのは、まったく誇張した表現ではない。朝8時過ぎに静岡駅で十山のスタッフに迎えられ、車で蒸溜所まで向かう。地図上ではそれほど遠くないようにも見えるが、目指す所在地は南アルプスの山中だ。曲がりくねった山道を進むには、特別な運転技術も必要である。幸いにして、この道を数百回も走った熟達者の運転なので心配はなかった。
乗り物酔いの予防薬を飲んで、いざ出発。午前11時過ぎになって、一般車両の立ち入りが制限されるゲートに到着した。このゲートから蒸溜所まで、さらに20kmの道のりが続くのだという。途中で元気な子グマが車を追い越していく。そして正午を少し回った頃、ようやく蒸溜所に到着した。
南アルプスの山中で
これまで日本や海外でたくさんの蒸溜所を訪れたが、井川蒸溜所ほど「奥地」という言葉にふさわしい場所はない。ついにやって来たのだという感慨にしばし浸った。
車を降りて、蒸溜所までの数百メートルを歩く。何時間も車内で縮こまっていた脚を伸ばしながら、蒸溜所の水源地を見に行くためだ。製造用水も工程用水も、蒸溜所で使用される水はすべてが木賊(とくさ)湧水から採っている。大倉喜八郎が購入した当時から、湧水が潤していたわさび田の跡が階段状に残っている。
水質は軟水(約40mg/L)で、水温は冷涼(9~14°C)。湧出量は豊富(200L/分)である。極めて純度が高い水なので、使用前に殺菌する必要がない。この水質を活かそうと、ウイスキー製造を始める前にボトル入り天然水の製造も検討された。しかし物流上の困難から、その事業は実現しなかった。
蒸溜所の製造施設と貯蔵庫は、大井川の上流に沿って建設されている。人の営みが途絶えた森の奥深くに、せせらぎを聞きながら佇む建物。この神秘的な光景に、興味津々の登山者が建物の正体を確かめようと近づいてくることもあるそうだ。そんな訪問者たちを迎えるのは、いつも蒸溜所所長の瀬戸泰栄さんだ。
瀬戸さんは、自身を含め総勢7人のチームを率いている。生産担当が6人、設備のメンテナンス担当が1人という構成だ。瀬戸さんは、以前は特種東海製紙で科学分析を担当していたが、ウイスキー事業の立ち上げに際して2人の同僚と共に参画を打診された。瀬戸さんが、その人選について振り返る。
「製紙会社でウイスキー製造のスタッフを探すのはもちろん初めてのことですが、採用基準はわりとシンプルでしたよ。お酒が好きで、科学の知識がある人です」
製造チームにはまだ人手が必要だったので、新たに3名のスタッフを採用した。立地が遠隔地ということもあって、スタッフは全員男性だ。
「蒸溜所の仕事は、現地で11日間連勤。その間は近くの山小屋に宿泊します。連勤が開けると、町に戻って4日間の休日があります。そして再び蒸溜所に戻って、また11日間働くという生活です」
ウイスキーづくりを完全に最優先したストイックな生活であることは間違いない。製紙業の分析担当者からウイスキー製造の現場への異動となるため、瀬戸さんは本坊酒造の蒸溜所で約1年間の研修を受けたのだという。
「2018年から2019年の大半をマルス駒ヶ岳蒸溜所で過ごし、そのうち1か月だけマルス津貫蒸溜所でも研修させてもらいました。駒ヶ岳蒸溜所は改装前だったので、多くの工程がまだ手作業でした。そういう意味で、たくさんの有益な学びがあったのは幸運でした。もともと大麦、糖化、発酵に関する知識はあったので、本坊酒造で学んだのはパラメーターにまつわる調整術です。科学的な知識があれば難しいこともありませんが、たった一人で派遣されたので荷は重かったですね」
井川蒸溜所での試験生産は2020年10月に始まり、その翌月から正式な生産が開始された。最初の樽詰めは12 月におこなわれている。人里離れた蒸溜所なので、コロナ禍による悪影響はほとんどなかった。
毎月の勤務体制は、前述のとおり営業日が22日で休日が8日という構成だ。昨年度までは大麦モルト1トンを1バッチとしていたが、今年からは1.1トンに微増させている。初年度(2020〜2021年)は40バッチを樽詰めして、初めてのフル稼働となった翌年度(2021〜2022年)には厳冬期も含めて120バッチをこなした。その翌年度(2023〜2024年)は、冬季にウイスキーの製造ができなかったため、100バッチの生産に留まったのだという。
「蒸溜所自体に問題があったわけではなく、宿泊施設の給水管が破裂したんです。入浴や洗濯などのため、蒸溜所からタンクで水を運んで大変でしたよ」
翌年度(2024〜2025年)は、このような厳しい状況を踏まえてあらかじめ生産量を80バッチに減らしたのだと瀬戸さんは明かす。
(つづく)