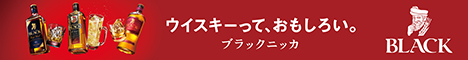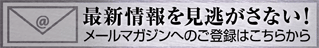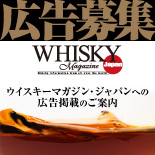雲上の井川蒸溜所を訪ねて【後半/全2回】
 最高の水源、野生の酵母、山深い熟成のゆりかご。卓越した製造技術を駆使しながら、アルプスの稀有な環境が極上のウイスキーを育てる。
最高の水源、野生の酵母、山深い熟成のゆりかご。卓越した製造技術を駆使しながら、アルプスの稀有な環境が極上のウイスキーを育てる。文・写真:ステファン・ヴァン・エイケン
井川蒸溜所で使用する大麦モルトは、スコットランドから輸入している。
「4種類の輸入大麦と1種類の国産大麦を試して、小さなコーヒーミルで麦汁を作って味比べをしました。スコットランド産の大麦が最も印象に残ったので、それを使用しています」
蒸溜所所長の瀬戸泰栄さんがそう説明する。大麦モルトはノンピートが主体だが、生産総量の20%をピーテッドモルトに充てているのだという。
「コンテナ1 つに大麦モルト20トンが入ります。ピーテッドモルトは全体の20%あるいは40%でやってきましたが、井川蒸溜所の目指すハウススタイルを考えると、40%は少し多すぎるかもしれないと思っています」
そして興味深いことに、このピートの強度には変遷もあるのだと瀬戸さんは言う。
「当初は2種類の強度のピーテッドモルトを使用していました。半分はミディアムピート(30ppm)で、残りの半分はヘビーピート(50ppm)だったんです。でも現在は、ライトピート(15ppm)の大麦モルトを使用しています」
ライトピートを使用することで、ニューメイクスピリッツに興味深い特徴が生まれたのだと瀬戸さんは語る。ヘビーピート(50ppm)では、ニューメイクにピートの香りが強く出る。ミディアムピート(30ppm)ならスモーク香とフレーバーのバランスが良くなる。だがライトピート(15ppm)では、予想外の効果も得られたのだという。
「煙っぽさがさほど感じられない代わりに、ある種のうま味がニューメイクに付与されたんです。ライトピートの大麦モルトを使ったのは今年度だけで、ウイスキーが熟成したときの結果はまだわかりません。来年はバランスを兼ね備えたミディアムピートに戻す予定ですが、将来はライトピートを増やす可能性もあります」
ピーテッドモルトのスピリッツは夏季に蒸溜され、それが終わった9月に設備のメンテナンスを実施する。だが昨年度はピーテッドモルトの納入が遅れたため、スピリッツ生産も冬まで続いたのだという。
「初めて冬季にピーテッドモルトのスピリッツを生産したので、風味が少し異なっているかもしれませんね」
山岳環境が育むクリアな酒質
蒸溜所の設備と製造工程は、ほぼ教科書通りだ。大麦モルトの製粉には、キュンツェル社製の6本ローラーミルを使用している。
「クリアなスピリッツを得るために、クリアな麦汁を目指して糖化します。麦汁が濁らないようにフラワーを少なめにして、少し粗めに製粉しています」
糖化以降の製造工程は、三宅製作所に特注した設備でおこなわれる。ウイスキー愛好家が注目すべきは、マッシュタンに垂直ピンホイール式マッシャーを採用した点であろう。井川蒸溜所は、この2018年に開発された新機能を日本で真っ先に導入した蒸溜所のひとつだ。三宅製作所のマッシュタンで、初めてアンダーバックを省略したモデルでもあるのだと瀬戸さんは説明する。
「周囲の温度に応じて、パラメーターの微調整が必要になります。最初の糖化は、お湯の温度を63°Cに設定していますが、たとえば冬場はステンレス製のマッシュタンが急激に冷えるため、タンクへの給湯時に68°Cまで上げておくこともあります」
糖化の2回目は、80°Cから段階的にお湯の温度を上げていく。その後、15分の循環を経てクリアな麦汁を得る。バッチあたり5,000Lの麦汁をウォッシュバックに送り、糖化の3回目(約2,000L)を次回バッチ用に確保する。
夏は30°C、冬は-15°Cという温度差が激しい条件下で、一貫した品質を追求しなければならない。そのため発酵には、流水ジャケット付きのステンレス製ウォッシュバックを採用した。同型のウォッシュバックは4槽あり、ジャケットは温水と冷水で温度を調整する。例えば発酵初日はウォッシュバックを軽く加熱し、48時間後には32°Cまで冷却してフルーツ香の発達を促している。全体の発酵時間は68時間で、アルコール度数約9%のウォッシュが得られる。
瀬戸さんは、井川蒸溜所で5種類の酵母を使用していることを誇らしげに教えてくれた。そのうち1種類はウイスキー用酵母、3種類はビール用酵母(エール酵母、ヴァイツェン酵母、ドラフト酵母)、最後の1種類が野生酵母だ。主要な生産プロセスとしては、ウイスキー用酵母とビール用酵母(1種類を選ぶ)を1:1の割合で併用している。
やはり気になるのは野生酵母だ。瀬戸さんいわく、野生酵母は南アルプスという自然環境を存分に活かしている。
「昨年から、蒸溜所周辺で採取した52種類の酵母を試してみました。まず十分にアルコールを生成できる野生酵母の種類を選び、その中から香味の良いものを選り抜きます。そして蒸溜所で使用可能な5つの候補に絞り込み、最終的にモクレンから採取した酵母に決定したんです。昨年は野生酵母で発酵させたウォッシュを1回だけ蒸溜し、樽3本分のニューメイクスピリッツを詰めました。現在は野生酵母株を乾燥酵母に加工する方法も探っています」
野生酵母のニューメイクスピリッツと、ノンピートのニューメイクスピリッツを比較しながら試飲させてもらった。この野生酵母プロジェクトが、単なる話題作りの大風呂敷でないとすぐに確信できた。野生酵母の複雑かつ斬新な香味は、ウイスキーファンを完全に魅了するだけの力がある。このスピリッツがオーク樽での熟成でどんな香味を発展させていくのか興味は尽きない。
次は蒸溜室だ。ポットスチル2基(容量8,000Lと5,000L)が、限りあるスペースに配置されている。両方のスチルを並べて写真に撮るのは難しい。どちらのスチルも蒸気で加熱され、ストレートヘッドと短めのネックが特徴だ。やや下向きのラインアームは、多管式(シェル&チューブ式)のコンデンサーにつながっている。
このような細部の設計は、すべてクリーンでクリアなスピリッツを抽出するためだ。蒸溜所は海抜約1,200メートルの高地にあるため、水の沸点は94°Cと通常よりも低い。もちろんアルコールの沸点も低くなるので、蒸溜工程でエステルが形成されやすいのだという。初溜と再溜にそれぞれ約7~8時間ほど費やし、バッチごとに約550Lのニューメイクスピリッツ(度数約68%)が得られる。バッチ11回分が得られたところで、スピリッツは度数62%に希釈されて樽に詰められる。
蒸溜時のカットポイントは、ピーテッドとノンピートで違いがない。蒸溜所でミドルカットの作業ができるのは3名のみだ。瀬戸さんによると、ニューメイクスピリッツの主要な香りは青リンゴとバナナであり、ミドルカット開始から約20分でヨーグルトのような香りも現れるのだという。
「華やかなニューメイクスピリッツを目指しているので、昨年までは比較的早めにテールをカットしていました。でも長期熟成を目指すという観点から、従来よりもテールカットを少し遅らせてみようと考え直したんです。今年はいわば二頭立ての戦略を採用しています。月の最初の11日間は早めにカットし、月の後半の11日間は少し遅らせています」
熟成の遅さもアルプスの個性
すべてのスピリッツが、現地で樽熟成されている。ラック式の貯蔵庫が2棟あり、収容力はそれぞれバレルで1,000本と3,500本である。貯蔵庫内の温度管理はしていない。樽材の割合はバーボン樽が約60%、シェリー樽が約30%で、残りの10%はブランデー樽、カルヴァドス樽、アイラ樽、ワイン樽などで構成される。また静岡県産の白ワイン樽も使用されている。
記念すべき1号樽はバーボン樽(ヘブンヒル)で熟成中だが、実は特別な0号樽も存在するという。現在は遠路はるばる蒸溜所まで足を運んでくる人たちの試飲用として保管されているのだという。この0号樽は、樹齢数百年のミズナラ材(倒木)から造られたパンチョン樽だ。ミズナラは、特種東海製紙が所有する土地で発見された。試飲させてもらったが(熟成4年強)、本当に特別で忘れられない香味だった。
「実はそのミズナラ材から容量450Lの樽を3本造ってもらったのですが、ミズナラ材は漏れやすいので、最終的に良い樽は1つしか残りませんでした」
蒸溜所周辺には木材が豊富にある。チームが有望なアイデアとして検討中なのは、ミズナラ材、サクラ材、クリ材などの現地で調達した木材から熟成樽のヘッド(天板)を製作することだ。
「特にミズナラ材の天板をはめ込んだバーボン樽は、将来的に井川蒸溜所のキーモルトを育ててくれる可能性もあります」
井川蒸溜所は、年間生産量約70,000Lという比較的小規模な生産拠点だ。ここでウイスキーをつくる事業に、忍耐が必要なのは言うまでもない。自然は急がせられないこともチーム全員が理解している。冷涼で湿潤な高地環境では、熟成が比較的ゆっくり進むのだと瀬戸さんは語る。
「熟成のピークまで、12年はかかると予想しています。でもそれで構いません。このゆっくりとした熟成のプロセスは、井川蒸溜所にとっても大切なものですから」
個人的なウイスキーの楽しみ方について、瀬戸さんに尋ねてみた。普段はよく「バランタイン10年」を水割りで味わうのだという。またシングルモルトでは、「ミルトンダフ」と「アバフェルディ」(共に12年熟成)を挙げた。
熟成が完了するまでの12年という道のりは長い。だが井川蒸溜所のスタッフたちは、ウイスキー愛好家たちと一緒にこの旅を続けていく決意だ。それまでの過程として、2022年からは「ラボシリーズ」の企画から「ニューボーン」と題されたウイスキーが順次発表されてきた。
そして2024年11月には、イラストをあしらったラベルにちなんで「デッサンシリーズ」と名付けられた数量限定のシングルモルトも発売している。このシリーズは「アルプスの植物と動物」をテーマとしたもので、毎年度末に「フローラ」を、翌年5月頃に「ファウナ」を交互にリリースする。フローラはノンピートの「直球」で、ファウナはピーテッドの「変化球」を表現しているのだと瀬戸さんは語る。
最初のリリースである「フローラ2024」と「ファウナ2025」は、どちらもバーボン樽熟成100%だった。「フローラ」はコンセプトに従ってノンピートだが、「ファウナ」はノンピート、ミディアムピート、ヘビーピートを組み合わせたウイスキーである。どちらもウイスキー愛好家から高く評価され、今年後半に発売予定の3作目「フローラ2025」にも期待が高まっている。バーボン樽での熟成をベースにしながら、シェリー樽熟成(ペドロヒメネスとクリームシェリー)の要素も加えられる可能性がある。
パッケージのデザインと仕上がりは、クラフトディスティラリーとしては稀有なほどに洗練されている。製紙会社が親会社なので、これは当然なのかもしれない。中味のウイスキーとパッケージデザインのつながりに思いを巡らせるのは、消費者にとって大きな楽しみの一部となるだろう。
最初の「フローラ」と「ファウナ」のリリースは、極めて限定的な数量となった。瀬戸さんによると、原酒をブレンドする新造のタンクが、容量5,000L(ボトル換算で約6,000本分)だからという説明だ。
静岡駅への長い帰路に備えながら、この場所にいる喜びを噛みしめていた。奥地の清らかな環境でウイスキーを製造する井川蒸溜所の努力に、あらためて感謝の思いが込み上げる。思いつきだけで、できるような事業ではない。チームの献身的な努力は、あらゆる称賛に値する。
そして山奥で熟成されるウイスキーの香味が、すべての努力をはっきりと反映している。最終的に、もっとも重要なのは個性と品質だ。ウイスキーが熟成されるにつれ、多くの愛好家たちも井川の旅に伴走したいと願うはずだ。長い旅になるだろうが、一緒に歩みを進められる幸せは何物にも代えがたい。