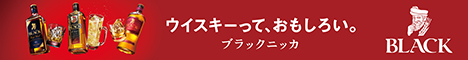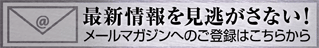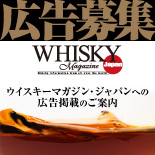ミズナラ樽の真実【前半/全2回】
 日本のみならず、海外のウイスキーメーカーも熟成に使い始めたミズナラ樽。その歴史と香味をあらためて探る2回シリーズ。
日本のみならず、海外のウイスキーメーカーも熟成に使い始めたミズナラ樽。その歴史と香味をあらためて探る2回シリーズ。文:マーク・ジェニングス
ウイスキー製造の世界では、ますます工程の効率化や情報の可視化が求められている。望み通りの香味を生み出すため、メーカーは選択したさまざまな工程の違いについてすぐに効果を確認したい。
そんな潮流に対して、静かな抵抗を続けている樽材。それがミズナラだ。扱いにくく、予測不能で、限られた人にしかおすすめできない難しい樽材だ。しかしその反面、ミズナラは現代のウイスキーで最も話題にのぼる樽材のひとつでもある。
幽玄な香りが漂い、どこか神聖な雰囲気を醸し出すウイスキー。そんな日本の伝統に紐づけられたイメージがミズナラへの評価を高めている。しかしミズナラにまつわる言説は、その多くが誤解に基づいているのだと識者はいう。そこには過大評価や、単なる事実誤認も含まれている。
今こそミズナラ樽が生まれた日本を訪ね、その歴史と現在の状況について学んでみたい。ミズナラ材は、どんな経緯でウイスキーの熟成に使用されるようになったのか。なぜ他の樽材よりも取り扱いが難しいのか。ふんだんに使われず、いつも少量の熟成のみに限定されている理由はあるのか。
ミズナラ(学名「Quercus crispula」)は、日本および北東アジアに自生するオーク(ブナ科 コナラ属)の一種だ。その日本名のように、高い水分含有量が特徴のひとつである。アメリカンホワイトオークやヨーロピアンオークとは異なり、ミズナラは成長がとても遅い。幹も曲がりくねったものが多く、たいていの木材に大きな節がある。
ミズナラ材がウイスキーの熟成に選ばれたのは、樽材が優れた風味をもたらしてくれるからではない。ただ単に、他の選択肢がなかったからだ。ジャパニーズウイスキーの専門書『ウイスキー・ライジング: ジャパニーズ・ウイスキーと蒸溜所ガイド決定版』を著したウイスキーライターのステファン・ヴァン・エイケンが説明する。
「ミズナラ樽の台頭は偶然の産物です。日本国内でウイスキーの生産が始まってから、数十年にもわたってミズナラの使用実績はごくわずかなものに留まっていました。ミズナラがジャパニーズウイスキーの個性を決定づけたという言説は、後世に生まれた想像上の俗説です」
ウイスキーがつくられるようになった日本では、第二次世界大戦の勃発から戦後にかけてオーク材の輸入が途絶える時期があった。そこでウイスキーメーカー各社は、地元産の木材を使った実験を始めることにした。その中で、最も有望だったのがミズナラ材である。しかし輸入材の代替として有望であるからといって、その熟成の効果が期待通りだったわけではない。
樽材として使用されるミズナラ材の扱いにくさについて、ジャパニーズウイスキーに詳しいウイスキー評論家のデイヴ・ブルームは説明する。
「ミズナラ樽は液体が漏れやすく、頻繁にひび割れが生じます。そして熟成にとても長い年月がかかるのも特徴です。ミズナラ材でウイスキーを熟成するには、まずこの基本的な特性を理解した上で、辛抱強く熟成期間のトラブルに対処していかなければなりません」
そうやって時間と労力を費やしても、熟成が成功するとは限らない。ミズナラは容赦のない樽材だ。なぜなら、そもそも品質にばらつきがある。樽材の良し悪しも、長い年月を経た後に、その効果が理解できる一部の人にしか判断できない。
日本の洋樽製造を担う有明産業を訪問
そんなミズナラの難しさを理解している人物の一人が、有明産業の営業部長を務める坂本賢弘さんだ。ミズナラの専門家でもある坂本さんが、ミズナラ樽の実際について語ってくれた。
「ミズナラの木目は不規則なので、アメリカンオークのように鋸で切ったりできません。手でていねいに割っていかなければ、あとから漏れが生じる原因になるんです」
有明産業は、日本唯一の独立系洋樽メーカーだ。日本では樽製造チームの多くが酒造メーカーの社内部門だが、有明産業は創業以来50年以上にわたって独立した専門業者として樽製造に携わってきた。創業当初より焼酎業界向けに樽を製造していたが、その後ウイスキー業界にも進出している。
サントリーやニッカなどの大手メーカーは、樽を自社で製造してきた。だが近年のクラフトウイスキーブームによって、日本国内のウイスキー業界も一変したのだと坂本さんは語る。
「自社で洋樽を製造できない新しい蒸溜所のみなさんから、注文をいただくようになりました。そこでミズナラ樽の生産を増やし、海外にも供給できるようになっています」
伐採した木材は、3年以上にわたって屋外で乾燥させる必要がある。それでもトーストの度合いによっては、樽板が割れてしまうこともあるのだと坂本氏は言う。
「トーストはなるべく低い温度で、しっくりと長い時間をかけておこないます。うまくトーストを仕上げるためには長年の経験が必要で、あらゆるプロセスを細かく調整しなければなりません」
有明産業が調達するのは、主に北海道のミズナラ材だ。北海道では木の成長がゆるやかなので、木目も他の地域より緻密な木材になるとされている。だがそんな最高の条件で育った原木でも、樽材に使用可能なのはごく一部分に過ぎない。残りは廃棄または他の用途に回される。これがミズナラ樽が高価な理由のひとつになっているのだと坂本さんは言う。
「ミズナラならみんな同じだと考える人もいらっしゃいますが、実際にはそれぞれの木に個性があります。木が異なるということは、つまり樽もそれぞれに異なっているということです」
そんな背景もさながら、実際のミズナラ樽には独特な存在感がある。金色のような淡い輝きを放ちながら、明らかに複雑な木目が貯蔵庫の中でもひときわ際立つ。静かな優雅さが漂い、秘密めいた印象も感じさせるのだ。
(つづく)