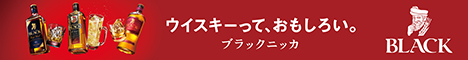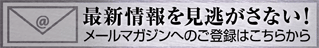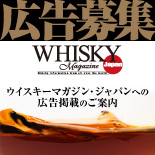北欧のウイスキー生産者たちが連帯する理由【前半/全2回】

地域社会との連帯やフラットな組織運営に長けた北欧諸国が、新しいウイスキー産地としての魅力を増している。ノルディックウイスキーの取り組みを探る2回シリーズ。
文:ヘザー・ストルゴー
スカンジナビアの国々には、もともと地域社会との連帯を重視する伝統がある。社会団体や有力な業界団体はもちろん、草の根的なボランティア活動も多くの人々に尊重されている。
ここ数十年で急速に発展したノルディックウイスキーシーンにおいても、この精神は生かされているようだ。さまざまな形のコラボレーションが、北欧諸国のウイスキー産業における重要な礎となりつつある。
いわゆる「ニューワールド」のウイスキーに懐疑的な保守層は、長年にわたって北欧のウイスキーメーカーに批判的な視線を向けてきた。それは後発の精力である北欧の新興メーカーたちが、アイリッシュやスコッチのメーカーによるケルト風のブランディングをが模倣しているという見方だ。

だがこれは完全な誤解である。北欧のメーカー各社は、ウイスキーを地域に根ざした産品にすることを強く望んでいる。彼らのウイスキーは、新北欧料理(ニュー・ノルディック・キュイジーヌ)の人気に牽引される形で、その地域ならではの飲食文化に触発されながら進化してきた。
新北欧料理とは、地元で手に入る旬の食材と伝統技法を基盤としながら、洗練された調理技術によって新しい境地を開拓する潮流だ。チューウイスキー(Thy Whisky)の共同創業者であるヤコブ・ステルンホルムが、そのような北欧ならではのアプローチについて説明する。
「私たちの活動の核心は、原材料に対して北欧的な解釈を加えること。使用する食材の出自を誠実に開示し、故郷のコミュニティと結びついていることが保証されなければなりません」
チューウイスキーの設立には、現代の小規模メーカーらしい経緯がある。それは伝統に深く根ざしながら、新たな挑戦を続けるデンマークのウイスキー蒸溜所というイメージそのものだ。
チューウイスキーの創業者であるエレンとマリーの姉妹が、コペンハーゲンに戻って家族経営の農場を引き継いだのは10年前のこと。その移住に付き添って、姉妹の夫であるアンドレアスとヤコブもやってきた。
そして4人の家族は、家族伝来の専門知識を活かして有機栽培の農場を営みながら、畑から瓶詰めまで最高品質の穀物でウイスキーをつくるファームディスティラリー(農場蒸溜所)を築き上げた。これまでに数々の栄誉を獲得し、地域に根差した個性あふれるウイスキーづくりに魅了された熱心なファン層を獲得している。創業者を代表して、ヤコブ・ステルンホルムが次のように語ってくれた。
「ここには、あらかじめ決められた方法など存在しませんでした。すべてが手探りの実験だったのです」
もちろん多くの苦労もあったが、前例がない環境は新しい正統を築くチャンスでもある。デンマークの国樹であるブナ材のスモーク香を加えたウイスキー「ボーグ」を発売したり、夏のウイスキーフェスティバルを開催して人気を博したり、新しい試みによって実績を積み上げてきた。
このような活動を続けていくうちに、デンマークだけでなく北欧産のさまざまなノルディックウイスキーが国際的に認知されるようになる。するとヤコブたちのような生産者は、より組織的な地域コミュニティへのアプローチが必要なのだと気づきはじめた。
そこで数年前に、チューウイスキー、ファリー・ローカン、スタウニングといったデンマーク国内のウイスキー業界の関係者が集まり、デンマーク産のウイスキー(ダニッシュウイスキー)の定義について議論が交わされた。このような取り組みの動機について、ヤコブは次のように振り返る。
「これまで私たちは新しいカテゴリーを築くために懸命に努力してきた訳ですが、出来上がったカテゴリーが何ら保護されていないことにも気づいたんです」
国別の協働から、北欧全体の連帯へ
こうした議論の集大成として生まれたのが「ダニッシュウイスキー宣言」だ。今年初めにコペンハーゲンで発表された宣言は、地元原料の使用、伝統的職人技に基づいた革新、サステナブルでトレーサブルな生産方針などを謳っている。ここにデンマークのウイスキー業界の原則が定められ、ダニッシュウイスキーがそれを遵守する誓いが立てられたのだ。
しかしこのような国レベルの連携も、現地メーカーの最終目標とは見なされていない。なぜなら、さらなる連帯の広がりを求める声があったからだ。デンマークの隣国スウェーデンでは、2023年に初めてとなる「ノルディック・ウイスキー・フォーラム」が開催された。北欧内外の蒸溜所代表者が集い、国際的な関心と品質評価が高まるスカンジナビア地域のウイスキーの将来像について議論が交わされることになった。
この画期的な会合が、新たな組織「ノルディック・ウイスキー・コラボレーション」の始動につながった。作業部会を通じた進捗は緩やかだが、将来像の模索から実務的な物流ソリューションまで幅広い分野での検討が進められている。今年初めにコペンハーゲンで開催された第1回の会合では、可能な限り包括的かつオープンな場を目指した。
そもそも北欧といえば、世界の中でも特にフラットな組織構造で知られる土地柄だ。オーロラ・スピリット蒸溜所のマーケティング責任者を務めるインギエル・ソールサンドは、参加した会合の印象について次のように語った。
「ごく小規模な蒸溜所から大手メーカーまで、あらゆる関係者が互いに学び合う意欲に満ちていました」
オーロラ・スピリット蒸溜所は、北極圏の山がちな半島にある世界最北の蒸溜所だ。このような立地から、さぞかし周囲からも孤立した僻地なのだろうと思われがちである。だがそれはまったくの誤解で、ウイスキー事業は周囲とのさまざまな助け合いによって運営されているのが実像だ。
オーロラ・スピリット蒸溜所が頼りにしているのは、北欧の内外にまで広がる業界ネットワークだ。共同創業者の一人はスコットランド出身で、スタッフもイングランドからラトビアまで多国籍のチーム。毎年春になると蒸溜所は操業を停止し、スタッフ全員で海外にあるウイスキー業界の関係者を歴訪するのだという。
そのような外部との連携に余念のないオーロラ・スピリット蒸溜所だが、地元とのつながりも同様に重視している。蒸溜所の貯蔵庫で最もエキサイティングなプロジェクトのひとつは、地域の農家たちとの協力で取り組む「アークティック・バーリー(北極の大麦)」だ。これは農業とウイスキー生産の限界を真に押し広げるようなプロジェクトである。
インギエル・ソールサンド(オーロラ・スピリット蒸溜所)とヤコブ・ステルンホルム(チューウイスキー)は、それぞれノルウェーとデンマークの代表としてこのプロジェクトで緊密に協力してきた。両蒸溜所の間には、1,600kmもの距離がある。だがその物理的な隔たりをものともせず、2 人は自分たちの仕事に共通の理解とアプローチを見出しているのだとステルンホルムは説明する。
「デンマーク、アイスランド、ノルウェーのウイスキーづくりでは、実際に同じような取り組みがたくさんおこなわれています。北欧をウイスキーの産地としている時点で、すでにある種の共通点があるのです」
たとえば機器や樽を長距離輸送する際に、輸送用のパレットを共有する。お互いのイベントにも参加し、会合でさまざまな問題解決について意見を交わし合う。このような同業者グループは、有用な知識を共有する素晴らしい方法だとソールサンドも考えている。
「ロビー活動から流通まで、あらゆる分野の専門知識を持った人々にアクセスできます。同じ課題を抱えながら、業界発展への情熱を共有できるのです」
(つづく)