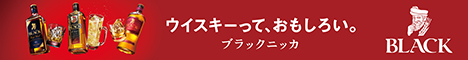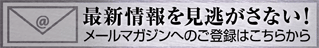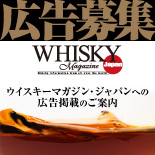未来が眠る、秩父蒸溜所の第1貯蔵庫
日本におけるクラフト蒸溜所のリーダーとして、新設蒸溜所の重要なモデルにもなっている秩父蒸溜所。ここ数年で樽作りのノウハウも蓄積され、熟成管理が新しい次元へと進化しつつある。このたび画期的な新樽が運び込まれたという第1貯蔵庫に潜入した。
文・写真:ステファン・ヴァン・エイケン
自社内で樽職人を育成し、熟成の幅を広げている秩父蒸溜所。その取り組みを「木と共に歩む秩父蒸溜所」と題して紹介したのは昨年秋のことだった。記事のなかでは、自前の樽工房で作られたアメリカンオーク新樽の第1号にも焦点を当てた。
あれから約1年が経った秩父蒸溜所は、さらに新しい段階へと歩みを進めている。その象徴が、蒸溜所内の樽工房で自作したミズナラ樽だ。これまでも樽職人たちがミズナラ材のヘッドを他の樽にはめ込んだ例はあったが、「カスク#6818」は蒸溜所内でスタッフがすべてを組み上げた100%ミズナラ樽の第1号である。
2011年以来、肥土伊知郎氏が率いる秩父蒸溜所のチームは毎年北海道の旭川に足を運んできた。日本最大の広葉樹丸太市「北海道産銘木市売」で、ミズナラの丸太を入手するためである。同業者のウイスキーメーカーはもちろん、高級家具メーカーも良質なミズナラ材を求めているので、入札はいつも激戦になる。家具メーカーが求める条件は比較的許容度に幅があるものの、ウイスキーメーカーの理想に適うミズナラ材は希少だ。お目当ては、柾目がまっすぐで節のない最上級の木材である。
今回完成した「カスク#6818」は、2011年初頭に購入したミズナラの丸太を材料にしている。丸太は購入から半年後に北海道で樽材に切り分けられ、同地で2年間にわたって空気乾燥された。その後、樽材は秩父に移されて、最大限に有効活用できるタイミングを待ち続けてきたのである。

さらにミズナラ材は、ウイスキーの熟成に使用される一般的なオーク材よりも扱いが難しい。樽材が通常のオーク材よりも分厚くなるため、樽形に湾曲させる際にひび割れてしまうリスクが高いのだ。秩父蒸溜所スタッフの言葉を借りるなら、「カスク#6818」はまさにサバイバー。蒸溜されたノンピートのスピリッツを入れて、このたび第1貯蔵庫に移されたばかりだ。背後の列には、秩父蒸溜所が自作した第1号樽の「カスク#3826」が眠っている。
フレーバーの幅を広げ、一貫性を保つためのカスク戦略
このミズナラ樽をひとつ作るのに、かなりの投資が必要だったのは想像に難くない。いったいどれくらいのコストを見込んでいたのかと尋ねると、ベンチャーウイスキーの肥土伊知郎社長はこう答えた。
「カスクひとつを作るのに必要なコストは、実際のところ計算したくありません。数字を見たら断念しちゃいそうで怖いんですよ」
できることは可能な限り蒸溜所内でやる。これは単なる自己満足ではなく、ウイスキーづくりの全段階で品質をコントロールできるようにするための戦略である。肥土氏は過去に独立系の樽工房からミズナラ樽を購入したこともあったが、完全に満足できる品質ではなかったという。樽材の柾目が、密に詰まっていないことにも気づいていた。しっかりとした柾目の樽材は、ウイスキーの熟成中に、木のフレーバーとアロマをより緩慢に授けて一体化させてくれる。これが熟成年を引き伸ばす際に都合がいいのである。柾目が詰まった樽材からはより豊かな木のアロマが得られるが、柾目がゆるい樽材は同じ時間でより多くのタンニンをスピリッツに放出することになる。

新しい大桶は、ベンチャーウイスキーのベストセラー「イチローズ モルト&グレーン ホワイトラベル」のマリッジに使用されている。モルト&グレーンは世界の5大ウイスキー生産地であるスコットランド、アイルランド、アメリカ、カナダ、日本のウイスキーをブレンドした商品。以前はバッチごとにボトリングされていたが、この新しい大桶でソレラシステムのマリッジが可能になるため、より一貫性のあるフレーバーで瓶詰めできるようになる。近い将来には、サイズも素材も同じ大桶があと2槽フランスから届くことになっている。
短期(ブレンドやマリッジ)と長期(通常の熟成)の両方で、秩父蒸溜所のスタッフは妥協のない一流品質の熟成を目指している。そこに投じられる労力や金額は相当なものになるだろう。だが彼らは、そんな努力が最終的に実を結ぶことを疑っていない。今から5年後、10年後、20年後、この樽で熟成されたウイスキーがグラスに注がれる時はやってくる。未来の人々が驚き、その風味が夢ではないと確かめる瞬間を、じっと心待ちにしているのだ。