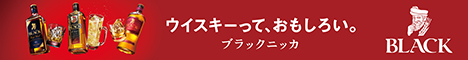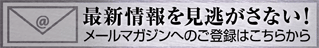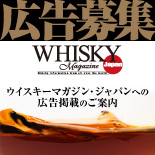チェコウイスキー探訪【前半/全2回】
 ビールやフルーツブランデーが有名なチェコ共和国で、ウイスキー製造が着実に成長している。スコットランドに比肩しうる品質への取り組みを追った2回シリーズ。
ビールやフルーツブランデーが有名なチェコ共和国で、ウイスキー製造が着実に成長している。スコットランドに比肩しうる品質への取り組みを追った2回シリーズ。文:ハリー・ブレナン
ピルスナービール発祥の地として、世界のビールファンを魅了してきたチェコ共和国。ウイスキーづくりも実践されているが、いわゆるワールドウイスキーの有力産地とは見なされていなかった。
それでもチェコのウイスキー産業は、まったくのゼロから始まった訳ではない。なぜならこの国には、何世紀にもわたる製麦とビール醸造の経験があるからだ。樽職人やスピリッツ蒸溜者(果実原料)もいるし、穀物、樽材、さらには泥炭に至るまで、ウイスキーに必要な優れた地元産の原料も手に入る。
地理的な条件や、文化的基盤もすべて整っている。量こそスコットランドには及ばないが、こと品質においては有名なウイスキー産地に比肩できる潜在力がチェコにはある。
スコットランドと同様に、地理的条件の多様性がチェコウイスキーの発展を支えている。その地域とは、ボヘミアとモラビアだ。ボヘミアは首都プラハを擁する地域で、面積も人口もモラビアを上回っている。ボヘミアの人口は約700万人で、モラビアは約300万人だ。チェコの国内には10軒のウイスキー蒸溜所が点在しているが、ボヘミアに7軒、モラビアに3軒なので、ちょうど人口の比率をそのまま反映した状況である。

近代におけるスコッチウイスキーの発展は、スコットランドのローランドとハイランドに支えられてきた。それと同様に、成長途上のチェコウイスキー産業もボヘミアとモラビアの双方に支えられている。それぞれに歴史と伝統がある両地域の組み合わせこそが、チェコウイスキーの魅力といってもいいだろう。
チェコの生活文化には、12世紀以来ずっとビール醸造と製麦の伝統が根付いている。大麦の栽培にはボヘミアの方が適しているものの、チェコ産の麦芽といえば多くがモラヴィア・シレジア州のブルンタール産だ。この地方では少なくとも500年にわたって麦芽が生産されている。
モラビアでウイスキーをつくっているトシュ蒸溜所とルドルフ・イェリーネク蒸溜所は、どちらも近隣のテシェティツェ村で栽培した大麦を製麦したブルンタール産モルトを原料に使用している。チェコ国内には最高品質のビール醸造所が数多く存在するので、チェコ産の大麦モルトを使用するのはわざわざ明記の必要がないほど地元の蒸溜所にとって当然の選択となる。
スコットランド以外で、地元産のピートを使用している数少ない国のひとつがチェコである。ラドリク蒸溜所とドラブカ蒸溜所は、フェノール値20ppm前後のスモークを施したシングルモルトを発売している。ルドルフ・イェリーネク蒸溜所のシングルモルト「ゴールドコック ピーテッド」は、州境を超えたボヘミアのホラ・スヴァテーホ・シェベスティアーナ町で採掘されたピートを使用したウイスキーだ。フェノール値30ppmの明瞭な燻香が人気となり、最近アルコール度数が45%に下げられたばかりである。
チェコのウイスキー蒸溜所には、酵母で地域色を表現しているところもある。プラドロ蒸溜所はチェコ産のパン酵母を発酵に使用しており、これはスウェーデンのマクミラ蒸溜所を思い起こさせるアプローチだ。発酵時間は蒸溜所ごとに幅があり、この点もスコットランドと同様だ。ルドルフ・イェリーネクの「ゴールドコック」がわずか3日間で発酵を完了させるのに対し、トシュはエステル形成を促進するため最大で12日間も発酵に費やすことがあるという。トシュは発酵後の蒸溜にもじっくりと時間をかける。
チェコ最古の蒸溜所がどこかという問題には、さまざまな見解があって結論が出ていない。グリーンツリー蒸溜所(Palírna U zeleného stromu)は1518年創業と自社で主張しており、これが事実なら欧州最古のウイスキー蒸溜所となる。創業年の根拠は、プロステヨフの住民数名に1518年にビール醸造の酒造免許が交付されたという記録だ。だがこれはあくまでビール醸造の話であり、スピリッツの蒸溜について書かれた記録は1610年以降に初めて現れる。当時は蒸溜技術が中欧に導入され始めたばかりであったが、それでもなお驚異的な歴史といえるだろう。
フルーツブランデーとビールの伝統を融合
グリーンツリー蒸溜所の古さは、世界最古のウイスキー蒸溜所と呼ばれるブッシュミルズ蒸溜所と比較しても印象深い。ブッシュミルズのボトルに記された「1610」は、アントリム州がウスケボーの製造免許をこの地域に与えた年を指している。現代のブッシュミルズは1784年創業であるため、グリーンツリーが欧州最古ではないかという主張は依然として信憑性を保っているかもしれない。
グリーンツリーが、1810年までにモラビア最大の蒸溜所となったのは確かな事実だ。ただし主力製品は、スリヴォヴィツェ(プラム酒)のような果実原料の蒸溜酒であった。チェコにおけるウイスキー製造は、この長い果実酒の歴史からバトンを受け継いだ比較的新しい事業である。それでもスピリッツ蒸溜の歴史だけを考えれば、チェコの伝統に比肩するスコットランドの蒸溜所はごくわずかしかない。
現代に近づくと、チェコのテシェティツェとプラドロで2軒のウイスキー蒸溜所が発展した歴史もある。テシェティツェ蒸溜所ではチェコ最初期のシングルモルト製品である「ゴールドコック」が製造され、1980年代を通じてチェコとソ連で販売された。その他、2010年代以前に出回ったもうひとつのチェコ産ウイスキー「ハンマーヘッド」はプラドロ蒸溜所の製品である。だが1989年のビロード革命後、すべての蒸溜所はスピリッツの蒸溜を停止。チェコウイスキーの復活は、2000年代まで待たねばならなかった。
既存の大手フルーツブランデーメーカーであるルドルフ・イェリーネクは、「ゴールドコック」ブランドを取得して2008年までにヴィゾヴィツェで新たな原酒の生産を開始した。同様にプラドロ蒸溜所も2010年にウイスキーの生産を再開している。幼少期から蒸溜所の敷地を駆け回っていたというプラドロ蒸溜所のクリスティナ・デメロヴァ(マスターディスティラー)は、足掛け12年でブランドの再建に取り組んできた。
ルドルフ・イェリーネクの「ゴールドコック」は、2013年から2014年の設備投資により生産体制を拡大した。ヴィゾヴィツェの緯度(北緯49.2度)にちなみ、アルコール度数49.2%で瓶詰めするという構想も実現されている。現行のラインナップは、2018年までにほぼ確立された。中でも「ゴールドコック 10年」ルドルフ・イェリーネクの主力商品だが、蒸溜所閉鎖前から持ち越されてきた在庫の原酒により「ゴールドコック 20年」も販売されている。プラドロ蒸溜所も復活した蒸溜所で製造した原酒のみから「プラドロ 10年」をボトリングしており、「プラドロ 18年」と「プラドロ 30年」には1980年代から持ち越されてきた在庫の原酒を使用している。どちらの製品も、チェコウイスキー自体が思ったほど新参ではないという証拠である。
テシェティツェ村で、チェコ共和国としては最初のウイスキーが生産されたのは1973年のことだ。この村にあるトシュ蒸溜所は、スピリッツ蒸溜の歴史を新しいスタイルのウイスキー製造と融合させている。そしてトシュ蒸溜所は、「コミュニティクラフト蒸溜所」を自称する2017年創業の新興メーカーだ。現在は15ヶ月熟成のスピリッツ「ラファイエット」と4年熟成のウイスキー(スモークフレーバー)「キングバーリー」を販売している。
チェコ共和国のウイスキー製造は、主にモラビアで始まった。だがグリーンツリーは、珍しくモラビアとボヘミアの両地域にまたがっている。グリーンツリーの主要銘柄はスタラミスリヴェツカ(オールドハンター)で、本社はウースチー・ナド・ラベム(ボヘミア)に、生産拠点はプロスチェヨフ(モラビア)にある。同社の「スタラミスリヴェツカ(オールドハンター)」は、スコッチならグレーンウイスキーと比較されそうなライ麦原料のウイスキーで、連続式のカラム蒸溜機で蒸溜されている。そのスピリッツを4〜7年間バーボン樽で熟成し、アルコール度数40%でボトリングしたものだ。
(つづく)