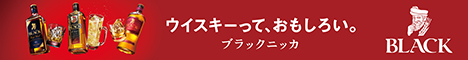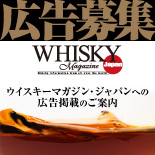ウイスキーの熟成とソレラシステム【後半/全2回】
 一貫性を目指すためのソレラもあれば、独創性を期待するソレラもある。いずれにしても、異なるタイプの原酒から望ましいブレンドの効果を得るのが目的だ。
一貫性を目指すためのソレラもあれば、独創性を期待するソレラもある。いずれにしても、異なるタイプの原酒から望ましいブレンドの効果を得るのが目的だ。文:ジョアンナ・デリー・ホール
自社蒸溜所のストックを持たないブレンダーたちにとっても、ソレラシステムの考え方は革新的なウイスキーを生み出すチャンスの源となる。トンプソン・ブラザーズはドーノッホで自社の蒸溜所を運営しているが、ブレンダー兼ボトラーとして買い取った他社の原酒からも独自のウイスキーをボトリングしてきた。
この時に、さまざまな樽で熟成された原酒を創造的に組み合わせる手段がソレラシステムだ。ソレラ式にブレンドされたウイスキー「SRV5」は、「ステーション・ロード・ヴァット5」の略。さまざまな原酒を入手した2022年末に、偶然生まれたウイスキーなのだと蒸溜所長のジャック・ロウリーは語る。
「この施設でウイスキーづくりを始めたとき、まず5槽のウォッシュバックを購入しました。でもよく考えたら、発酵室に5槽も置くスペースがなかった。そこでブレンド用の容器に転用したんです」
前回の記事で紹介した「グレンフィディック パーペチュアル」も、この「ドーノッホSRV5」も、厳密な定義によるソレラシステムでつくられている訳ではない。だが容器から原酒の一部を取り出し、減った分を補填するという原則は共通している。しかし「ドーノッホSRV5」は、容器に蓋がない点でグレンフィディックとは大きく異なる。この点についてロウリーが語る。
「昔のブレンダーの手法をいろいろな書物で調べてみると、原酒をマイリングして休ませながら一体化させる工程が常に重要視されていました。時間をかけて、緩やかに酸化させるため、容器は不活性な木樽を使用するのが基本。そうすることで、ウイスキーの各バッチの香味が重層的になっていくのだと思われます」
マリイングのレシピは一貫しているにもかかわらず、蓋のないオープントップの容器はかなり特殊な貯蔵環境だ。原酒は空気中に漂っているあらゆる粒子に晒されるし、温度の変化にもすぐ反応するためバッチごとに微妙な違いが生まれる。夏場は蒸発を抑えるためにシートで覆っているが、ローリーは予想外の変化を受け入れているようだ。
「こういう非効率なところにこそ、意外な風味を発展させる可能性があると割り切っています」
実験精神から選ばれたソレラ的なアプローチ
エディンバラのポート・オブ・リース蒸溜所でも、ソレラシステムの考え方を生かしたウイスキー「パーペチュイティ」がつくられている。ブレンダーのサム・トラヴァースは、ソレラの実験的な側面に興味をそそられているのだと楽しげに語る。
「ジョニ黒みたいなウイスキーの対極にあるようなブレンデッドウイスキーをつくりたいと思っていました。徹底した管理と計算ではなく、タイムカプセルのように何が出てくるかわからないワクワク感。毎回バッチごとに仕上がりが異なるブレンデッドウイスキーがあってもいいじゃないかという考え方です」
サム・トラヴァースは、2つの事業を同時に進めていた。ひとつはジンのリンド&ライム、もうひとつがエディンバラの波止場に新設されたポート・オブ・リース蒸溜所でのウイスキーづくりだ。だがウイスキーは熟成に時間がかかるので、それまでの間にどんな工夫を凝らせるのかを思案していたのだという。そんな実験精神が、革新的なアイデアにつながったのだ。
「私たちは新米なので、大量の在庫を抱えて悠々と待っていられるような老舗のウイスキー会社とは違います。ブローカーや友人から原酒をいろいろ購入したものの、その品質がまちまちであることに翻弄されていました」
特定のスタイルを目指して架空のレシピを組んでも、必要な原酒を確保できないのが独立系ボトラーの限界だ。そこで代わりに、自分たちが調達できるものから何が生み出せるのかを考えたのだという。
「限られたバリエーションのウイスキーを想定するのではなく、『ウルトラバリエーション』と呼べるほど多様なポートフォリオになってもいいと割り切ったら、ソレラシステムのようなアイデアが役に立ったんです」
第1弾の「パーペチュイティ」では、ディーンストン(バーボン樽熟成)、グレントファース(シェリー樽熟成)、英国北部のウイスキー(英国産オーク新樽熟成)の原酒を使用。第2弾ではミルトンダフ(シェリー樽熟成)、インヴァーゴードンのグレーン原酒(リフィルのシェリー樽で17年熟成)、グレンマレイ(リフィル樽熟成)、英国北部のウイスキー(英国産オーク新樽7年熟成)、英国北部のウイスキー(英国産シェリーホグスヘッド樽4年熟成)、ベンネヴィス(リフィルのペドロヒメネスシェリー樽熟成)を購入して加えた。
この第2弾の原酒も、すべて最初のバッチに追加する形でマリイングされているのだとトラヴァースは語る。
「同じ名前の商品なのに、最初のバッチから一体どこまで香味が逸脱できるのか。これはクリエイティブな選択になります。ソレラのような優れたシステムを利用するというより、何か新しいものを創造したいという欲求から生まれたアイデアなのです。そもそも新しいウイスキーをつくりたいと思って始めた事業なので」
このようなソレラシステムの活用法には、ハンナ・ウイスキー・マーチャンツ社長のグレガー・ハンナも賛同している。同社が輸出市場向けにボトリングしているブレンデッドウイスキー「セントブリジットカーク」も、ほぼ同じ考え方に基づいた商品だからだ。
「独立系ボトラーは、スピリッツの発酵や熟成で遊ぶことができません。できるのは、入手できたスピリッツで最大限の仕事をすることだけです」
独立系ボトラーとして、ハンナはウイスキーのフィニッシュ(追熟)にソレラシステムを採用している。まとまった量のボトリングで残った原酒を使い切る知恵でもあるため、毎回ブレンドのレシピは異なってくる。
他のメーカーはソレラ式の熟成工程に不活性な樽や容器を選ぶが、ハンナはまだ現役のフィノシェリー樽1本とオロロソシェリー樽2本で独自の小規模なソレラシステムを構築している。これは原酒が樽を移動しながら、それぞれの樽から多彩な個性を獲得できるフィニッシュの仕様だ。
「これは実験なのです」とハンナは言い切る。このアプローチの楽しさは、まさに実験という言葉に要約されるのだろう。
ソレラシステムをヒントにしたマリイングによるブレンドの構築が、スコッチの可能性と創造性を広げてくれる。そこから生まれる商品には、シングルモルトもあればブレンドデッドもある。熟成年数を記してもいいし、記さないことを売りにしてもいい。一貫した香味を保てることもあれば、変幻自在の香味を生み出すこともある。
ウイスキーづくりの探求に終わりはない。